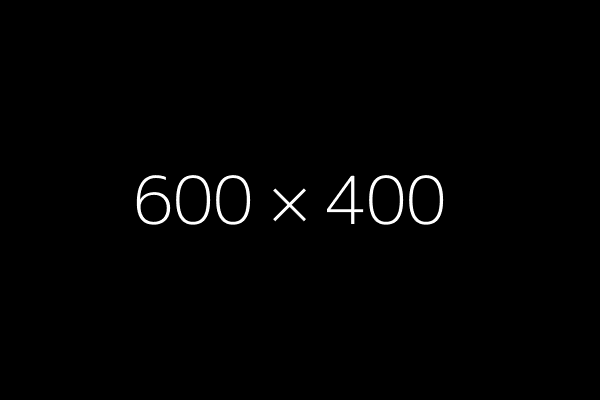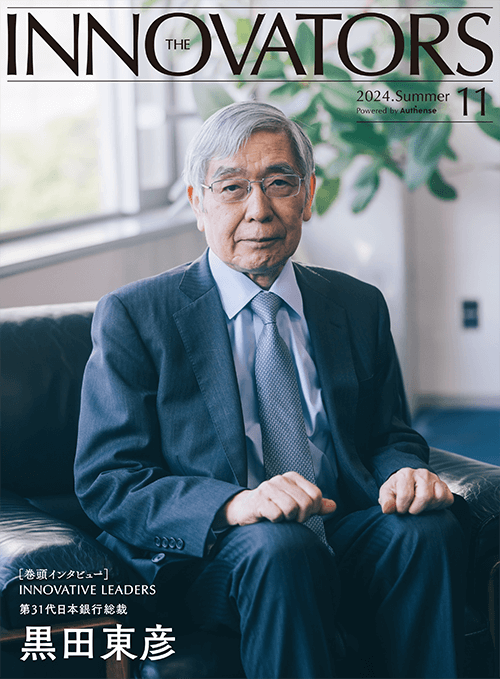「製造物責任法(PL法)」について聞いたことはある一方で、十分に理解できていない事業者も少なくないようです。
しかし、商品の製造や販売、輸入などをする事業者は、製造物責任法を理解しておかなければなりません。
製造物責任法とはどのような法律なのでしょうか?
また、製造物責任法で責任を負う事業者の範囲は、どこまでなのでしょうか?
今回は、製造物責任法の概要や製造物責任法に対応するために企業が講じるべき主な対策を、弁護士がわかりやすく解説します。
目次

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
製造物責任法(PL法)とは
製造物責任法とは、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定める」法律です(製造物責任法1条)。
これにより、被害者の保護を図ることや、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが目的とされています。
「製造物責任」は英語で「Product Liability」と表記されることから、略して「PL法」と呼ばれることもあります。
製造物責任法の存在意義は、製品の欠陥により消費者が損害を受けた際における責任追及を容易にすることです。
製造物責任法がなかった場合、消費者は民法の規定を根拠として事業者に責任を追及することとなります(民法709条)。
しかし、民法を根拠として事業者に不法行為責任を問うためには、責任を追及しようとする消費者側が事業者の過失を立証しなければなりません。
事業者の内部事情を知り得ない消費者が過失の存在を立証することは不可能に近く、泣き寝入りせざるを得なくなる可能性が高いでしょう。
そこで、製造物責任法ではこの民法の規定を修正し、製造業者等は「その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」こととされています(製造物責任法3条)。
つまり、製品の欠陥などにより被害を被った消費者は、事業者の過失までを立証せずとも、製品の欠陥の存在やその結果により損害が生じたことさえ立証すれば、事業者への責任追及が可能になるということです。
ただし、消費者の財産や身体などには損害が及ばず、その製品が壊れただけであれば、製造物責任法は適用されません(同条但し書き)。
また、次のいずれかの事実を事業者が立証したときは、事業者は免責されます(同4条)。
- その製造物をその事業者が引き渡した時における科学・技術に関する知見では、その製造物にその欠陥があることを認識できなかったこと
- 次のすべてに該当すること
- 1.その製造物が、他の製造物の部品または原材料として使用された
- 2.その欠陥が専らその他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じた
- 3.その欠陥が生じたことについて自社に過失がない
製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」の要件
製造物責任法の対象となる「製造物」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
ここでは、「製造物」の要件について解説します(同2条1項)。
「動産」であること
1つ目は、「動産」であることです。
動産とは、不動産以外のすべての財産を指します。
土地や建物、樹木などの不動産は、原則として製造物責任法の対象とはなりません。
ただし、建物を構成する部品などに欠陥があった場合には、製造物責任法によって責任を追及できる可能性があるため、お困りの際は弁護士へご相談ください。
有体物であること
2つ目は、有体物であることです。
有体物とは一般的に、空間の一部を占める有形的な存在を意味します。
一方で、電気やソフトウェアなどの無体物は、製造物責任法製造の対象とはなりません。
なお、「ソフトウェアが搭載されたパソコン」は有体物であるため、パソコンが発火して負傷したなどの場合には製造物責任法の対象となります。
「製造・加工」されたものであること
3つ目は、製造・加工されたものであることです。
未加工の農林畜水産物は「製造・加工」されたものではないため、製造物責任法の対象とはなりません。
製造物責任法(PL法)で責任を問われる「欠陥」とは
製造物責任法で事業者が責任を問われる「欠陥」について、製造物責任法では次のように定義されています。
- 当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
つまり、その製品を通常の用法で使用した際に、通常有すべき安全性を欠いている状態が「欠陥」ということです。
たとえば、子供用の鉄棒であれば子どもがぶら下がることを前提としており、対象年齢の子どもがぶら下がっただけでこれが折れて怪我をした場合、製造物責任法の「欠陥」と判断される可能性が高いでしょう。
一方で、たとえ形状が似ていても物干し竿は人がぶら下がることを前提とはしておらず、消費者が室内用物干し竿にぶら下がった際にこれが折れて怪我をしても、「欠陥」と判断される可能性は低いと考えられます。
また、安全性に関わらないような単なる品質上の不具合は、製造物責任法の「欠陥」には該当しないとされています。※1
製造物責任法(PL法)による責任を負う事業者の範囲
製造物責任法で責任を負う事業者は、通常の意味での「製造者」に限られるわけではありません。
ここでは、製造物責任法で責任を負う事業者の範囲を解説します。
特に、「輸入をした事業者」や「製造業者と誤認させるような氏名などの表示をした事業者」は、自社は製造物責任法の責任を負わないと誤解していることも多いため注意が必要です。
また、いずれも法人のみならず、個人事業者も該当します。
製造・加工をした事業者
1つ目は、業として製造物を製造・加工をした事業者です(同2条3項1号)。
製造した事業者はもちろんのこと、加工をした事業者も対象である点にご注意ください。
また、「業として」とは、事業活動の一環として反復継続して行うことを指します。
ただし、今後継続して行う予定がある場合において、偶然最初の行為であったからといって「業として」に該当しなくなるわけではありません。
なお、「設置」や「修理」をした事業者は、原則として製造物責任を負う対象にはならないとされています。※1
輸入をした事業者
2つ目は、業として製造物を輸入した事業者です(同2条3項1号)。
輸入をしただけで製造などをしていない場合、製造物責任法の対象になるとは考えていないケースは少なくないでしょう。
しかし、輸入をした事業者は、製造物責任法の責任対象となることが法律に明記されているため、十分に注意しなければなりません。
特に、個人で海外から製品を輸入し、これをインターネット上などで販売するビジネスは散見されます。
このような場合であっても、業として行っている以上、製品に欠陥があり消費者に損害が生じた場合は製造物責任法に基づいて責任を問われる可能性があります。
お困りの際は、お早めに弁護士へご相談ください。
製造業者と誤認させるような氏名などの表示をした事業者
3つ目は、製造業者と誤認させるような氏名などの表示をした事業者です(同2条3項2号)。
表現がわかりにくいものの、OEMやいわゆるPB(プライベートブランド)などがこれに該当します。
たとえば、製造機能を有していないA社がB社に委託して製品Xを製造してもらった場合、実際の製造業者はB社です。
しかし、商品ラベルには製造業者としてA社の名称を付した場合、消費者はこれをA社が製造したものと考えるのが自然でしょう。
このような場合には、製造業者であるように表示したA社が、製造物責任法の責任主体になるということです。
なお、欠陥品を納入したことについてその後A社はB社に責任を追及できる余地はあるものの、これは製造物責任法とは別の話であり、消費者にも直接的な関係はありません。
製造物責任法(PL法)への企業の主な対応策
製造物責任法に備え、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
最後に、製造物責任法への企業の主な対策を解説します。
製造物責任は回避できないことを理解しておく
対策の前提として重要となるのは、製造物責任を100%回避することはできないと理解することです。
製品の販売や加工、輸入などを行う以上、多かれ少なかれ製品の欠陥は生じます。
企業努力によって世に出てしまう欠陥品をできるだけ少なくしたり、仮に問題が生じても重大な被害が及ばないようにしたりすることは可能であるとはいえ、それでも欠陥をゼロとすることは困難でしょう。
また、消費者が一方的に不利益となる契約は消費者契約法の規定により無効となるため、契約や約款などで製造物責任を回避することもできません。
そのため、製造物責任法への対策を講じる前提として、責任の回避はできないことを理解することが重要です。
適切な警告表示をする
先ほど解説したように、製造物責任法の欠陥とは、その製品の用法に応じて有すべき安全性を欠いている状態を指します。
その製品の適切な用法などを製品に表示することで、誤った利用により事故が生じる事態を避けやすくなるほか、自社の責任を回避しやすくなります。
また、製品の用法について特に注意すべき点がある場合には、図などを使ってわかりやすく表示するとよいでしょう。
なお、これらの表示をパッケージだけに行った場合には、開封時に捨てられる可能性が高くなるほか、商品に直接貼った場合であっても使用とともに剥がれる可能性もあります。
そのため、その製品が通常使用される年数や用途などを踏まえ、使用期間中に剥がれたり読めなくなったりしないよう表示を工夫することをおすすめします。
社内の危機管理体制を整備する
製造物責任法への対策としては、社内の危機管理体制の整備も重要です。
先ほど解説したように、製品を製造などしている以上、欠陥をゼロにすることは難しいといえます。
しかし、欠陥に気づいた際に速やかに対応をすることができれば、欠陥による事故までは避けられる可能性が高くなります。
対応の代表例は、リコールです。
欠陥の可能性がわかった時点で早期にリコールをすることで、その欠陥による重大事故の発生を抑止できます。
とはいえ、リコールには莫大な費用を要します。
欠陥により事故につながる可能性が低い場合、リコールまでするかどうかは難しい経営判断となるでしょう。
しかし、迷っているうちに事故が生じてしまった場合、取り返しがつきません。
社内の危機管理体制を構築しておくことで、このような場合であっても速やかに対応しやすくなります。
PL保険に加入する
製造物責任法への対策としては、PL保険への加入も有効です。
PL保険とは、製造物責任法により責任を問われた際の賠償金や弁護士費用の支払いなどに備える保険です。
リコールに要する費用を補償する保険商品もあるため、自社が取り扱う製品の特性などに応じて加入を検討するとよいでしょう。
いざという時に弁護士に相談できる体制を構築する
製造物責任を問われる事態となった場合、初期の対応が非常に重要です。
そのため、万が一の際にすぐに弁護士へ相談できる体制を構築しておくことをおすすめします。
製造物責任法にくわしい弁護士へ早期に相談することで、初手から適切な対応がとりやすくなります。
また、製造段階における警告表示の内容などについても相談でき、より確実な対策が可能となるでしょう、
まとめ
製造物責任法の概要や企業が講じるべき対策などを解説しました。
製造物責任法とは、製品の欠陥などにより被害を被った消費者が事業者へ責任追及をするハードルを下げる法律です。
民法の不法行為責任を問うには消費者側で事業者の過失を立証する必要があるところ、製造物責任法があることで、欠陥の存在とその欠陥により損害を受けた事実のみを立証することで事業者の責任を追及できます。
事業者としては、欠陥をゼロにはできないことを認識したうえで、適切な警告表示をしたりPL保険に加入したりするなどの対策を講じるとよいでしょう。
また、相談できる弁護士を見つけておくことで状況に応じた具体的な対策のアドバイスが受けられるほか、問題が発生した際にもスムーズな対応をとりやすくなります。
Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームをも設けており、製造物責任法に関する助言やサポートも可能です。
製造物責任法に対応できる体制を構築したい場合や、製造物責任を問われてお困りの場合などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。