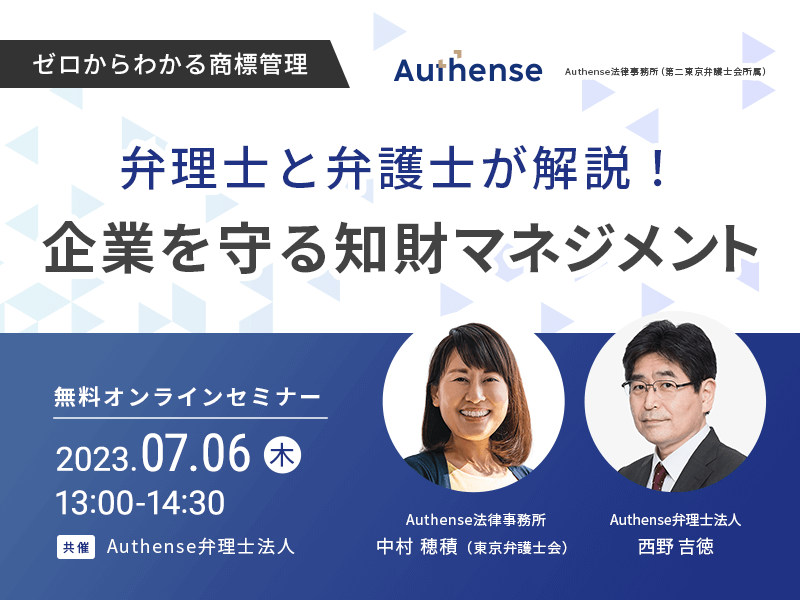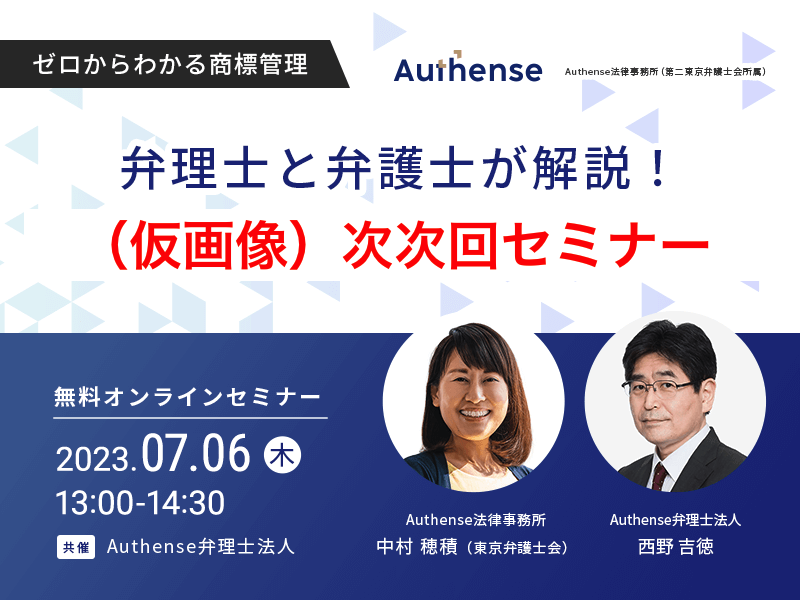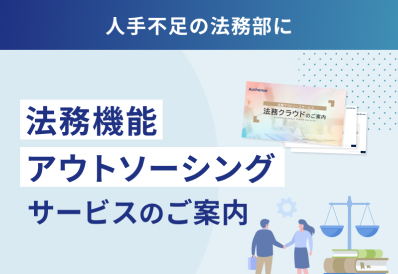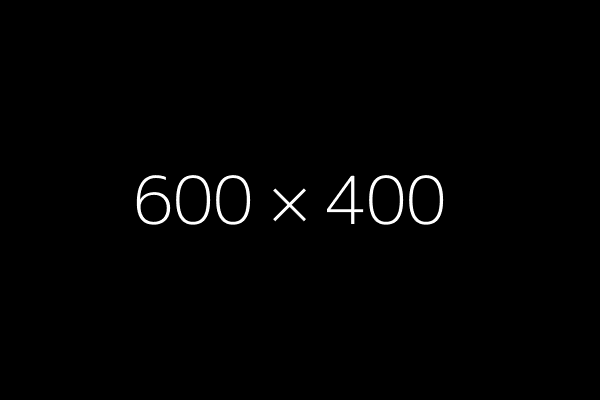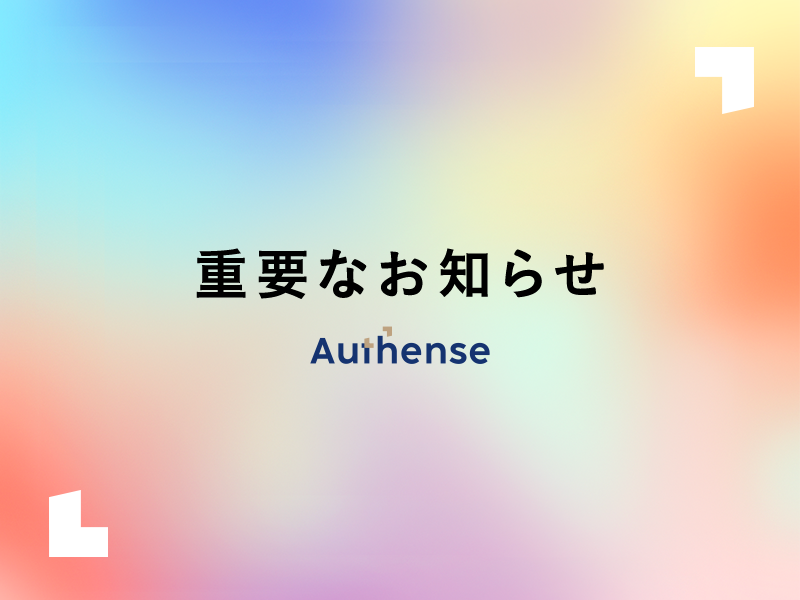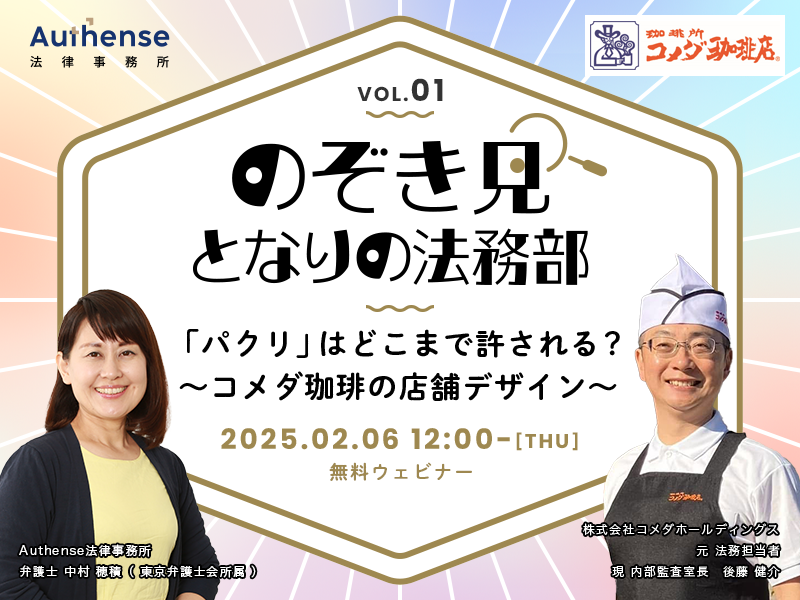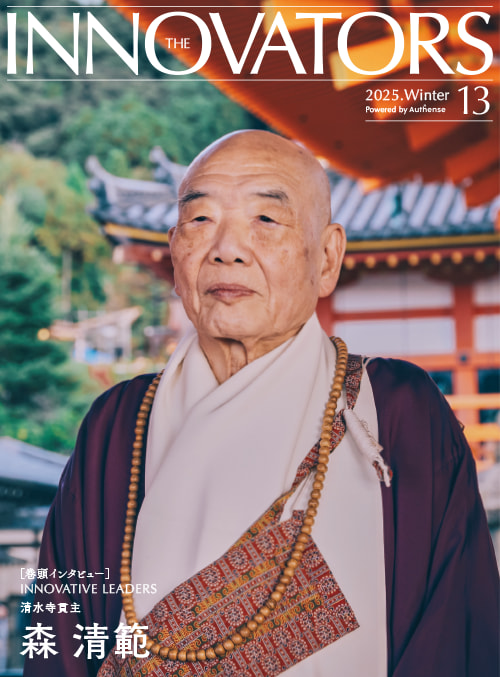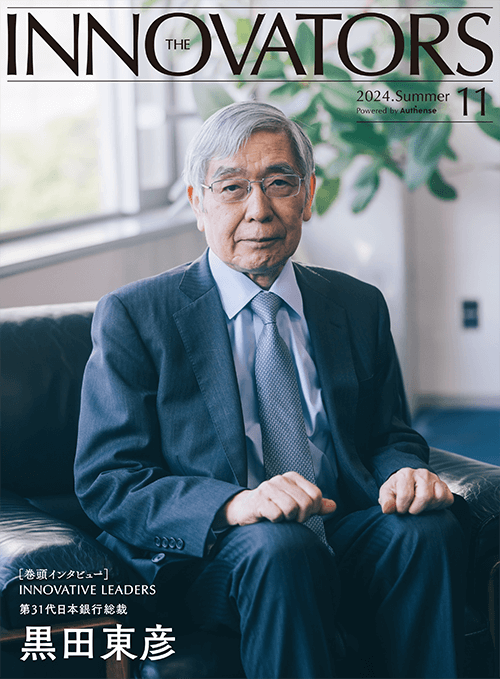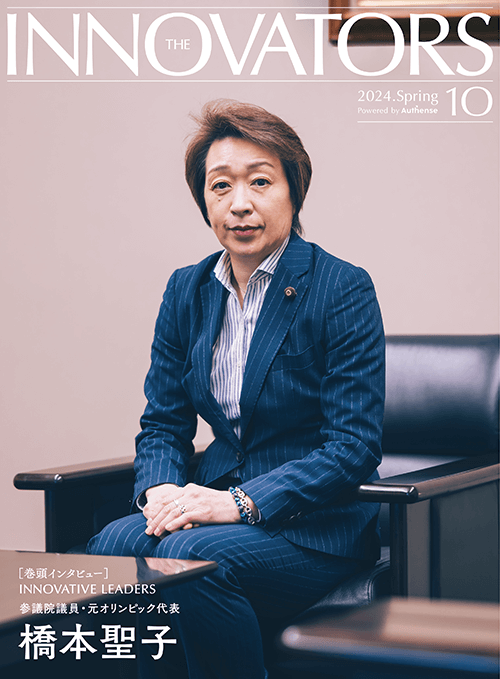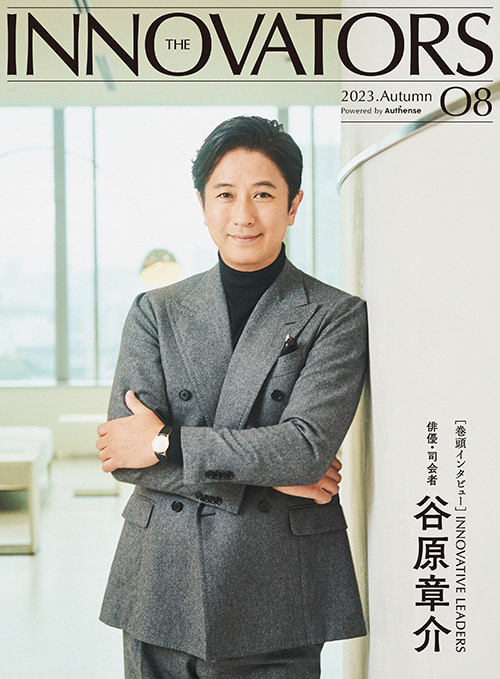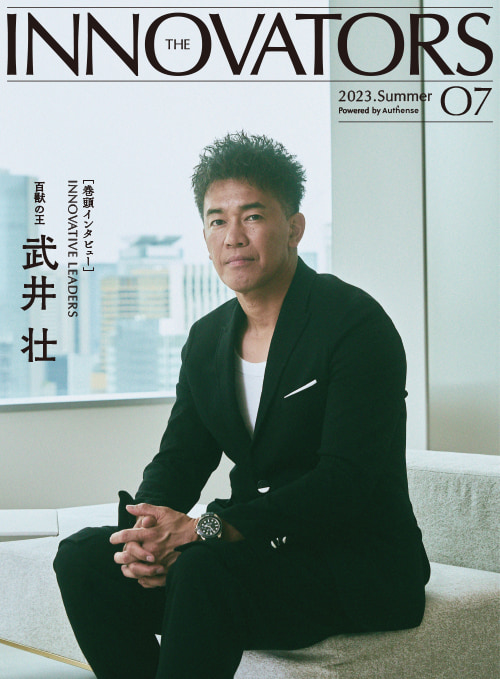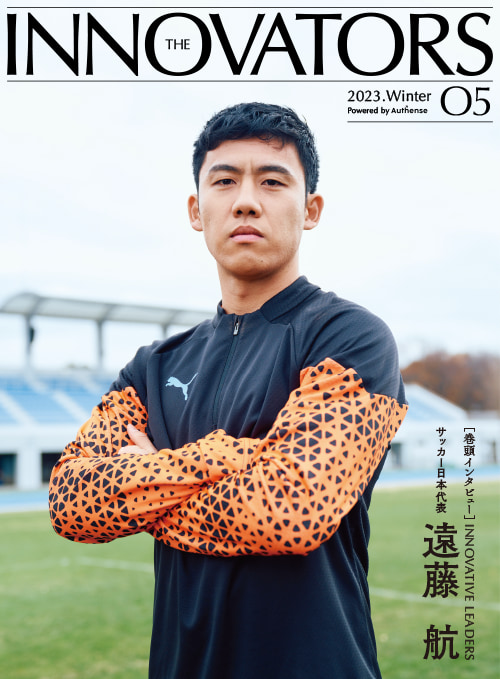廃棄物処理業を営む企業はもちろんのこと、廃棄物処理法は一般の企業も理解しておくべき法律の一つです。
廃棄物処理法を正しく理解していなければ、処理委託先が問題を起こした際に自社も法的責任を問われるおそれがあるためです。
では、廃棄物処理法とはどのような法律なのでしょうか?
また、廃棄物処理法では、主にどのような規制がなされているのでしょうか?
今回は、廃棄物処理法の概要や企業が理解しておくべき廃棄物の種類、廃棄物処理法の規制内容などについて弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
廃棄物処理法とは
廃棄物処理法は、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」を目的とした法律です(廃棄物処理法1条)。
ゴミの処理について適正な規制がなければ、有害なゴミが空き地で燃やされるなどして生活環境を悪化させるおそれが生じます。
また、ゴミの処分について委託を受けた企業が山林や海洋に不法投棄をすれば、自然環境も大きく悪化することでしょう。
そのような事態を避けるため、廃棄物処理法ではゴミ(廃棄物)の適切な分別や処理の方法などを定めています。
廃棄物処理法による廃棄物の主な分類
廃棄物処理法において、廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。
いずれに該当するかによって適法に処理を委託できる事業者も異なることから、企業は自社が出すゴミについてどちらに該当するか正しく理解しておかなければなりません。
たとえば、産業廃棄物の収集運搬業許可しか有していない事業者に一般廃棄物の収集運搬を委託すると、自社も罪に問われる可能性があるということです。
また、企業から出るゴミがすべて産業廃棄物に分類されるわけでもありません。
産業廃棄物と一般廃棄物について、それぞれ概要を解説します。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次のものなどを指します(同2条4項、産業廃棄物処理法施行令2条)。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず(建設業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものなどに限る)
- 木くず(建設業、木材・木製品・家具の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るものなどに限る)
- 繊維くず(建設業、繊維工業に係るものなどに限る)
- 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
- と畜場においてとさつし、または解体した獣畜など係る固形状の不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
- 鉱さい
- 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
- 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る)
- 動物の死体(畜産農業に係るものに限る)
ここで注意すべきは、「燃え殻」や「汚泥」のように事業活動から生じた限りはすべて産業廃棄物に分類されるものがある一方で、「紙くず」や「木くず」のように排出された業種によって産業廃棄物となるか否かが異なるものがあることです。
たとえば、出版業から排出された紙くずは産業廃棄物である一方で、弁護士事務所から排出された紙くずは産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されます。
このように、廃棄物の種類によっては業種ごとに取り扱いが異なるため注意が必要です。
なお、産業廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性があるなど人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれのあるものは、「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
特別管理産業廃棄物の処理委託は、特別管理産業廃棄物について許可を受けている事業者を選択して行わなければなりません。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します(同2条2項)。
事業活動に伴って排出されたものではない廃棄物(家庭ごみなど)のほか、先ほど解説したように、弁護士事務所から排出された紙くずなども一般廃棄物に分類されます。
なお、一般廃棄物のうち事業から排出されたものを「事業系一般廃棄物」といいます。
一般廃棄物であっても、事業系一般廃棄物であるものは、市区町村のゴミ集積所には出せない決まりとなっていることが一般的です。
廃棄物処理法の主な規制内容
廃棄物処理法では、どのような規制が定められているのでしょうか?
ここでは、排出事業者に課されている規制を中心に、廃棄物処理法の主な内容を解説します。
排出事業者の責任
廃棄物処理法では、排出者責任を定めています(同11条)。
これは、産業廃棄物の処理責任が原則として排出事業者にあることを定めたものです。
ただし、例外的に、許可を有する事業者に処理を委託することは認められています。
つまり、「処理業者に任せた時点で自社は責任を免れる」ということではなく、適切な処理業者を選定しなかった結果不適切な処理がされた場合には、排出企業も責任を問われ得るということです。
産業廃棄物の処理・保管基準
産業廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理・保管基準を定めています(同12条、12条の2)。
これは、事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合や運搬されるまでの間保管する場合などにおいて、一定の基準に従うべきことを定めた規定です。
自社が出したゴミであるからといって自由に保管すればよいのではなく、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。
保管場所の届出義務
産業廃棄物処理法では、保管場所の届出義務を定めています。
これは、排出した事業場の外における300㎡以上の場所で廃棄物を保管する場合に、事業者に届出を義務付ける規定です(同12条、廃棄物処理法施行規則8条の2の2)。
自社が管理する土地でさえあれば自由に廃棄物を保管できるわけではないため、届出を失念しないようご注意ください。
委託事業者の選定基準
産業廃棄物処理法では、委託事業者の選定基準について定めています。
これは、排出事業者が廃棄物の収集運搬や処分などを委託する場合において、必要な許可を有する事業者を選定すべきという規定です(同12条5項)。
産業廃棄物収集運搬業の許可を有していない事業者に産業廃棄物の収集運搬を委託できないことはもちろん、特別管理産業廃棄物の処理委託は、特別管理産業廃棄物処理の許可を有している事業者に委託しなければなりません。
適切な許可を有しない事業者に委託すると、罰則の適用対象となります。
処理状況確認の努力義務
産業廃棄物処理法では、処理状況確認の努力義務が定められています。
これは、排出事業者が他の事業者に廃棄物の収集運搬や処分を委託した場合において、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分が終了するまでの一連の処理行程が適切に行われるための措置を講じるよう努める義務です(同12条7項)。
つまり、排出事業者は廃棄物の処理を「丸投げ」して終わりではなく、委託先の事業者において適切に処理がされていることを確認するよう努めるべきということです。
マニフェストの交付義務
産業廃棄物処理法では、マニフェスト(管理票)の交付義務について定められています(同12条の3)。
マニフェストとは、廃棄物の適正な処理を確認するために用いられる用紙であり、排出事業者が廃棄物の処理を委託するにあたり、委託先の事業者に廃棄物とともに交付するものです。
その後、その廃棄物が適正に処分までなされると、マニフェストが排出事業者のもとへ戻ります。
なお、昨今では紙ではなく電子のマニフェストが使用されることも少なくありません。
また、一定の場合には、電子マニフェストが義務付けられています(同12条の5)。
多量排出事業者の計画提出・報告義務
産業廃棄物処理法では、多量排出事業者の計画提出・報告義務が定められています(同12条9項)。
多量排出事業者とは、前年度における産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者を指します(廃棄物処理法施行令6条の3)。
多量排出事業者は、その事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
廃棄物処理法に違反した場合の主な罰則
廃棄物処理法には刑事罰が定められており、違反した際には刑事罰の適用対象となる可能性があります。
ここでは、廃棄物処理法違反への主な罰則について解説します。
不法投棄、不法焼却等
廃棄物の不法投棄や不法焼却の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(同25条1項14号、15号)。
また、適切な許可を有さない者に廃棄物の収集運搬や処分を委託した場合も、同様の刑事罰の対象となります(同6号)。
無許可営業
必要な許可を受けないまま廃棄物の収集運搬や処分を事業として行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科の対象となります(同25条1項1号)。
無許可営業の罰則は不法投棄などと同じく重く設定されているため注意が必要です。
なお、許可を受けるには一定の要件を満たす必要があり、不正や虚偽によって許可を得た場合も同様の罰則の対象となります(同2号)。
マニフェストの交付義務違反等
マニフェストの交付義務に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(同27条の2)。
懲役刑もあり得る重い罰則が設定されているため、マニフェストの交付を失念しないようご注意ください。
企業が廃棄物処理違法に違反しないための対策
企業が廃棄物処理法に違反しないようにするためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
最後に、廃棄処理法に違反しないための主な対策を4つ解説します。
廃棄物処理法や関連するガイドラインを確認する
1つ目は、廃棄物処理法や関連するガイドラインを確認することです。
一般企業が廃棄物処理法に違反する場合、認識不足によるものであることが少なくありません。
廃棄物処理の責任は排出者にあることを理解したうえでガイドラインなどを読み込むことで、違反を抑止しやすくなります。
廃棄物の種別を正しく理解する
2つ目は、廃棄物の種類を正しく理解することです。
廃棄物を正しく処理したり、適切な処理事業者に委託したりするためには、自社から排出される廃棄物について正しく理解しておかなければなりません。
知らずに違反をしないためにも、廃棄物の種類について理解を深めておきましょう。
廃棄物の処理費用を必要なコストとして認識する
3つ目は、廃棄物の処理には相当のコストがかかることを認識することです。
「必要なものを購入することに費用がかかるのは仕方ない」と考える一方で、「ゴミを捨てることにあまりお金をかけたくない」と考える企業は少なくないでしょう。
しかし、家庭ゴミであれば自治体がサービスの一環で行っているため費用が掛かりにくい一方で、事業系ゴミは排出者の責任で処理しなければなりません。
そして、適切な廃棄物処理には費用が掛かるものです。
コストを抑えようとし過ぎた結果、よく確認しないまま必要な許可を持たない事業者や不法投棄などをする悪質な事業者に処理を委託してしまうと、排出事業者としての責任を問われかねません。
そのため、適正な廃棄物処理には費用がかかることを十分に認識しておくべきでしょう。
対応に迷ったら弁護士へ相談する
4つ目は、対応に迷ったら弁護士へ相談することです。
廃棄物処理法の解釈や判断に迷ったら、無理に自社で判断せず、弁護士などの専門家へご相談ください。
弁護士へ相談することでそのケースにおける最適な対応についてアドバイスを受けられ、廃棄物処理法に違反する事態を避けやすくなります。
まとめ
廃棄物処理法の概要や主な規制内容、違反時の罰則や違反しないための対策などを解説しました。
廃棄物処理法とは、廃棄物の適正処理などについて定めた法律です。
委託を受けて他者の廃棄物を収集運搬したり処分したりする事業者の許可制度や、マニフェスト制度などについて定められています。
なかでも注意すべきであるのは、廃棄物処理法は排出者責任を原則としていることです。
つまり、事業者は廃棄物処理を他社に委託したら責任を免れるものではなく、自社が排出した廃棄物には最後まで責任をもたなければなりません。
廃棄物処理法への対応で判断に迷った際には、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、廃棄物処理法に関するご相談にも対応が可能です。
廃棄物処理法に関してお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。