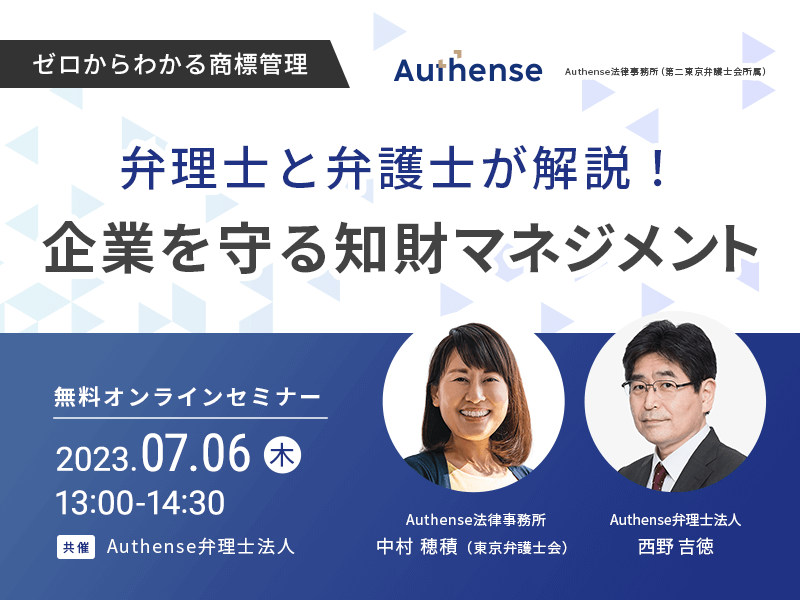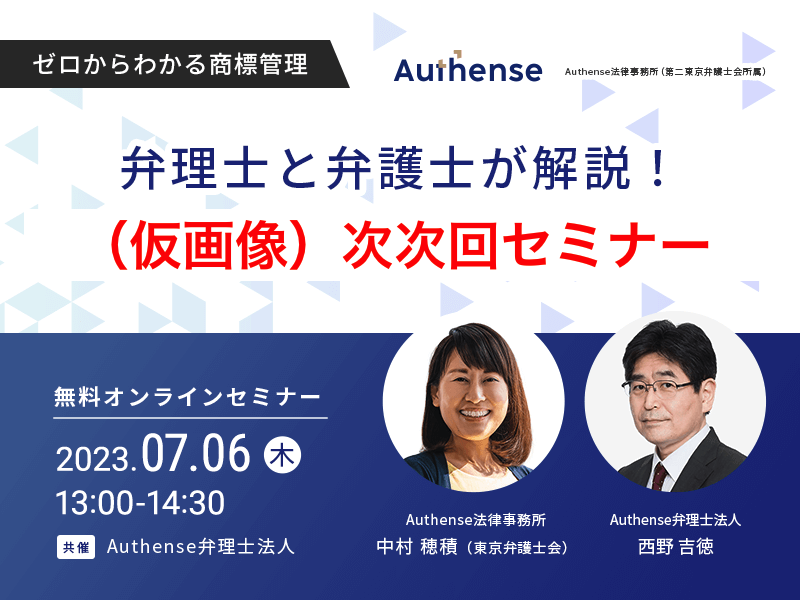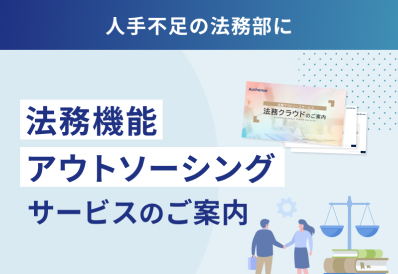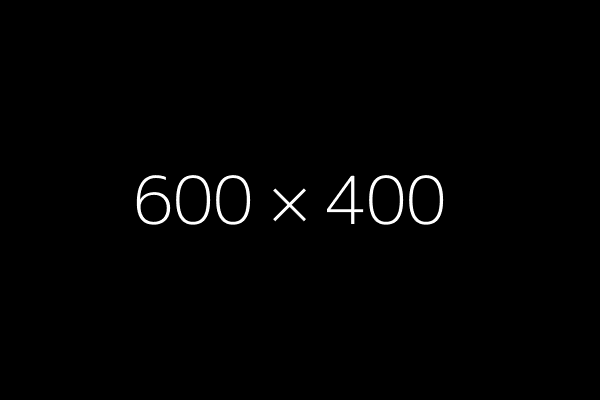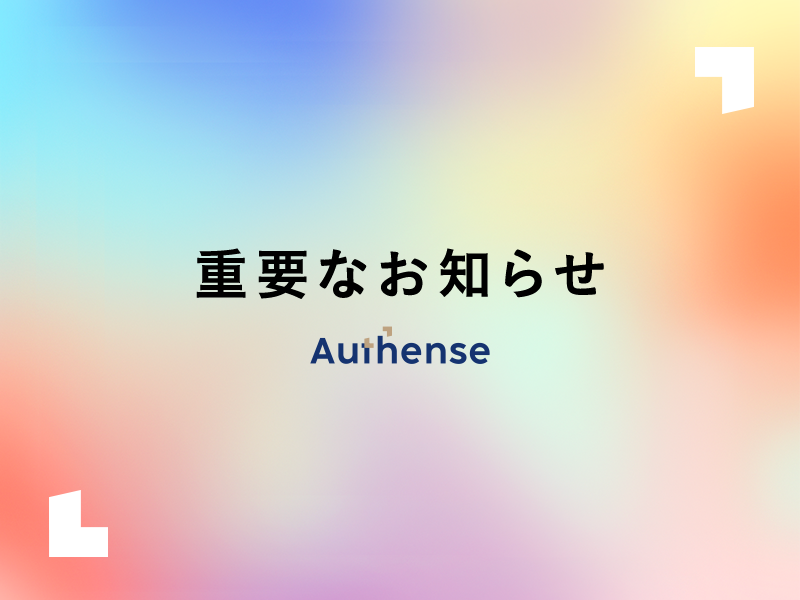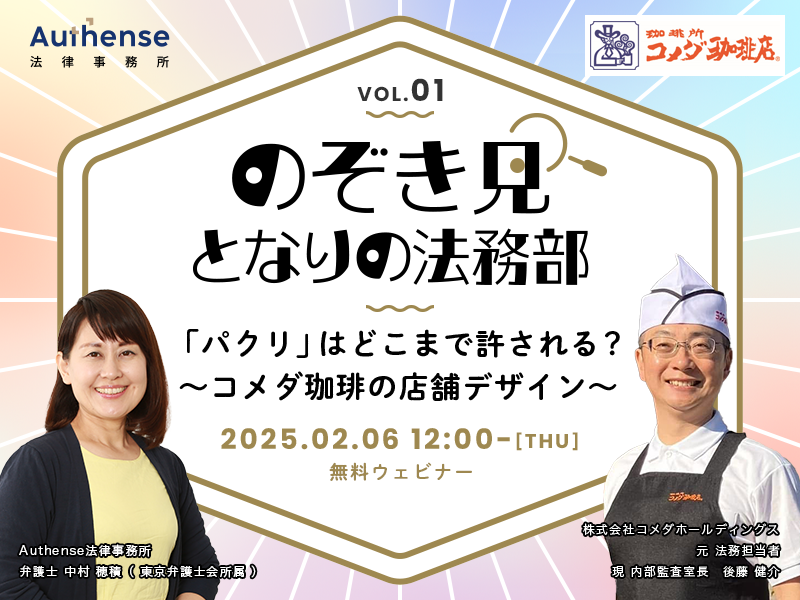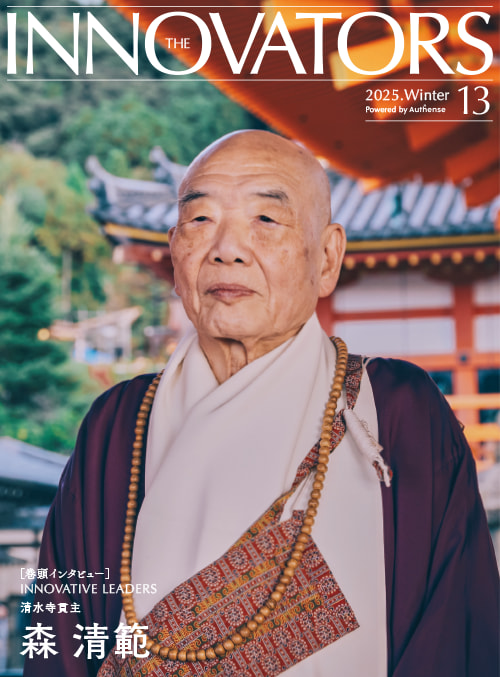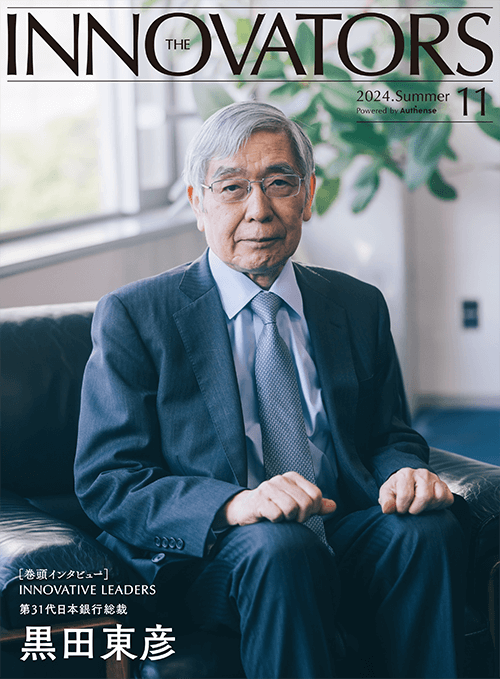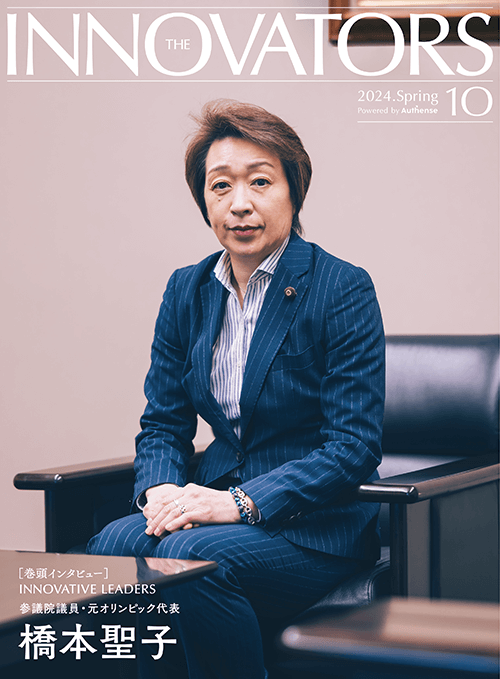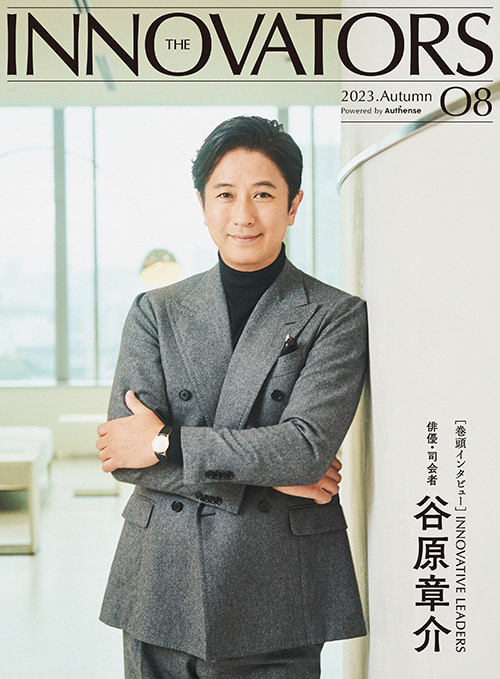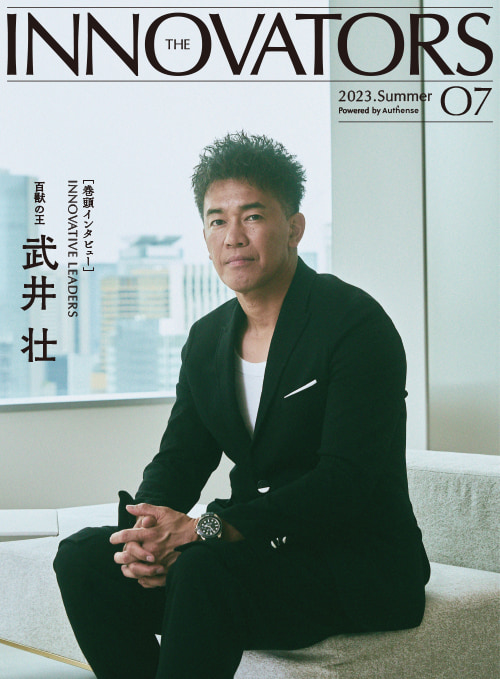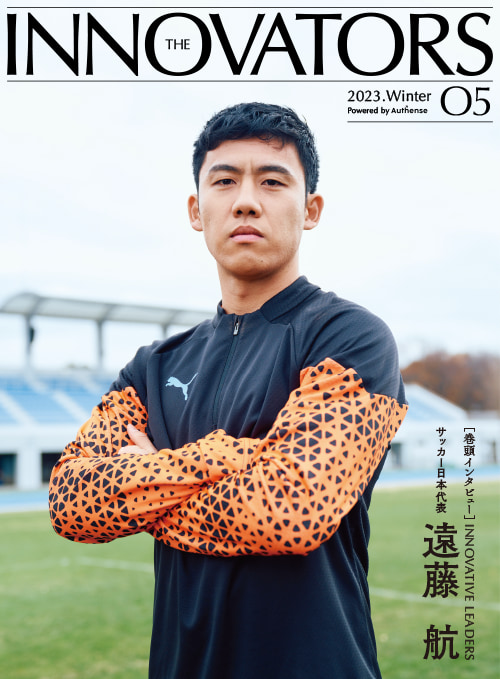「中小企業である」ことが要件とされている補助金や助成金は少なくありません。
しかし、中小企業の定義について、よく理解できていないケースも多いようです。
では、中小企業とは、どのような企業を指すのでしょうか?
また、これについて定めている「中小企業基本法」とはどのような法律なのでしょうか?
今回は、中小企業基本法の概要や中小企業の範囲、中小企業基本法の変遷などについて弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
中小企業基本法とは
はじめに、中小企業基本法の目的と基本理念を紹介します。
目的
中小企業基本法では、目的について次のように定めています(中小企業基本法1条)。
- この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
これによると、中小企業基本法の目的は、「中小企業に関する施策を総合的に推進」することと、これにより国民経済の健全な発展と国民生活の向上を図ることです。
この目的を達成するために、次の内容などを規定しています。
- 中小企業に関する施策の基本理念・基本方針などを定める
- 国と地方公共団体の責務等を明らかにする
この前提を把握しておくと、条文を理解しやすくなるでしょう。
基本理念
中小企業基本法では「基本理念」が定められています(同3条)。
中小企業基本法を理解する上ではこの基本理念を知っておく必要があるため、やや長いもののまずはそのまま記載します。
- 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
- 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たっては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、独立した小規模企業者の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。
「1」ではまず、中小企業が価値ある存在であることが述べられています。
ここで挙げられている中小企業の意義は次のものなどです。
- 多様な事業の分野において特色ある事業活動を行う
- 多様な就業の機会を提供することで、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供する
- 我が国の経済の基盤を形成している
そこで、次の重要な使命を有するとされています。
- 新たな産業の創出
- 就業機会の増大
- 市場における競争促進
- 地域における経済活性化の促進
このような背景を受け、「独立した中小企業者の自主的な努力が助長されること」が望ましいとされています。
これを実現するために、次の事項などによって多様で活力ある中小企業の成長発展が図られるべきというのが、基本理念の1つ目です。
- 経営の革新と創業の促進
- 経営基盤の強化
- 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
そして、基本理念の「2」では、小規模企業の活力発揮が重要である旨が述べられています。
中小企業の多様で活力ある成長発展のため、小規模企業は次の重要な意義を有するとされています。
- 地域の特色を生かした事業活動を行う
- 就業の機会を提供する
- これらにより、地域における経済安定と地域住民の生活向上、交流促進に寄与する
- 将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与する
小規模企業はこのような重要な役割を担っていることから、中小企業と同じく「独立した小規模企業者の自主的な努力が助長される」ことが望ましいとされています。
そのため、これらの事業活動に資する事業環境の整備により、小規模企業の活力が最大限に発揮されるべきこととされています。
このような基本理念をもとに、補助金や助成金などの中小企業施策が実施されています。
中小企業の範囲
「中小企業」の範囲は、実は法律によって異なります。
そのため、「中小企業」が何かの要件となっている際などには、どの法律に基づく「中小企業」であるのかよく確認しなければなりません。
ここでは、中小企業基本法による中小企業の範囲と、その他の法律による中小企業の範囲について解説します。
中小企業基本法による中小企業の範囲
中小企業基本法による中小企業の範囲は業種ごとに異なり、それぞれ次のとおりです(同2条1項)。
| 業種 | 中小企業者(いずれかに該当する場合) | |
| 資本金額または出資総額 | 常時使用する従業員数 | |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
なお、政令によって「ゴム製品製造業(一部を除く)」では、「資本金3億円以下または従業員900人以下」、「旅館業」は、「資本金5,000万円以下または従業員200人以下」、「ソフトウエア業・情報処理サービス業」は、「資本金3億円以下または従業員300人以下」の場合に中小企業に該当する場合があります。
そのため、実際に補助金などの施策に申請しようとする際は、その補助金などが指定している政令などもご確認ください。
(参考)会社法による中小企業の範囲
会社法では中小企業についての定義はない一方で、「大会社」については定義されています。
会社法における大会社とは、「資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社」です。
これに該当しない会社が中小企業とみなされます。
会社法上の大会社には、「会計監査人による監査を受ける義務」など、中小企業にはない義務が課されます。
(参考)法人税法による中小企業の範囲
法人税法では、中小企業に当たる企業を「中小法人等」といいます。
中小法人等に該当するのは、原則として資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人です。
ただし、資本金等の額が1億円以下であっても、大法人等(資本金等の額が5億円以上の法人)との間に完全支配関係がある場合には、中小法人等から除外されます。
法人税法で中小法人等に該当する場合には、法人税の軽減税率などの対象となります。
(参考)租税特別措置法による中小企業の範囲
租税特別措置法では中小企業の定義はされていない一方で、次のいずれかに該当する法人が「大規模法人」と定義されています。
- 資本金または出資金が1億円超
- 常時雇用する従業員の人数が1,000人超
これに該当しない法人は、中小企業とみなされます。
租税特別措置法の中小企業に該当する場合には、「取得価額30万円未満の固定資産の即時の損金算入」などの税制優遇措置の対象となります。
中小企業基本法の変遷
中小企業基本法は、どのように改正されてきたのでしょうか?
ここでは、中小企業基本法の主な変遷について解説します。
1963年:中小企業基本法の制定
中小企業基本法は、1963年に制定されました。
中小企業庁のホームページによると、この当時の中小企業は「一律でかわいそうな存在」と認識されていたようです。※1
そのため、中小企業基本法では中小企業と大企業との格差是正が中心とされていました。
1999年:中小企業基本法の抜本的改正
1999年、中小企業基本法が抜本的に改正されました。
この改正により、「中小企業=弱者」との構図が撤廃され、中小企業が次の役割を有する存在であるとされました。
- 新たな産業の創出
- 就業の機会の増大
- 市場における競争の促進
- 地域における経済の活性化
先ほど解説した、2025年時点における基本理念に近づいた形です。
そのうえで、次の3つが政策の柱とされました。
- 経営の革新及び創業の促進
- 経営基盤の強化
- 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
2013年:中小企業基本法の再改正
2013年の改正では、中小企業よりさらに小規模である「小規模企業」に対する中小企業施策の方針が新たに設けられました。
併せて、小規模企業振興基本法が制定されています。
中小企業基本法で定められている基本的施策
中小企業基本法では、具体的な施策が定められているのではなく、中小企業へ向けた基本方針が定められています。
最後に、中小企業基本法で定められている4つの基本的施策を紹介します。
中小企業の経営の革新及び創業の促進
1つ目は、中小企業の経営の革新と創業の促進です。
ここでは、国が次の3つの施策を講じるとの規定が置かれています(同12条から14条)。
- 中小企業者の経営革新を促進するための、新商品・新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進・商品の生産販売を著しく効率化するための設備の導入の促進・商品の開発、生産、輸送、販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進などの施策
- 中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するための、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策
- 中小企業の創造的な事業活動を促進するための、商品の生産・販売・役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保、資金調達を円滑にするための制度の整備などの施策
中小企業の経営基盤の強化
2つ目は、中小企業の経営基盤の強化です。
ここでは、国が次の施策を講じるべきとされています(同15条から23条)。
- 経営資源の確保(中小企業者の事業用施設や設備の設置・整備の促進、技術に関する研究開発の促進など)
- 海外における事業展開の促進(海外における事業の展開に関する情報提供、研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給など)
- 情報通信技術の活用の推進(情報通信技術の活用に関する情報提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給など)
- 交流または連携・共同化の推進(中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成など)
- 産業の集積の活性化(同種または関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている産業の集積活性化のために必要な施策など)
- 商業の集積の活性化(商店街など商業の集積の活性化を図るために行う、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備など)
- 労働に関する施策(職業能力の開発・職業紹介の事業の充実など)
- 取引の適正化(下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進など)
- 国等からの受注機会の増大(中小企業者の受注の機会の増大など)
経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
3つ目は、経済的社会的環境の変化への適応の円滑化です。
ここでは、次の場合において、国が中小企業の経営安定化と事業転換を円滑化するための施策などを講ずるべきことが定められています(同24条)。
- 貿易構造、原材料の供給事情などの経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、ある地域またはある業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがある場合
資金の供給の円滑化及び自己資本の充実
4つ目は、資金の供給の円滑化及び自己資本の充実です。
ここでは、国は次の施策を講じるべきこととされています(同25条、26条)。
- 資金の供給の円滑化(政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正融資の指導など)
- 自己資本の充実(中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化など)
まとめ
中小企業基本法の概要や主な基本的施策、中小企業の定義などを解説しました。
中小企業基本法とは、中小企業について国が講じるべき施策の方針などを定めた法律です。
実際に、中小企業基本法の規定に従い多くの補助金や融資制度などが設けられています。
中小企業基本法を理解しておくことで、中小企業へ向けてどのような施策が講じられているのか全体像を把握しやすくなるでしょう。
Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、中小企業基本法に関する相談にも対応しています。
中小企業基本法や、これに基づいて展開されている具体的な施策について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。