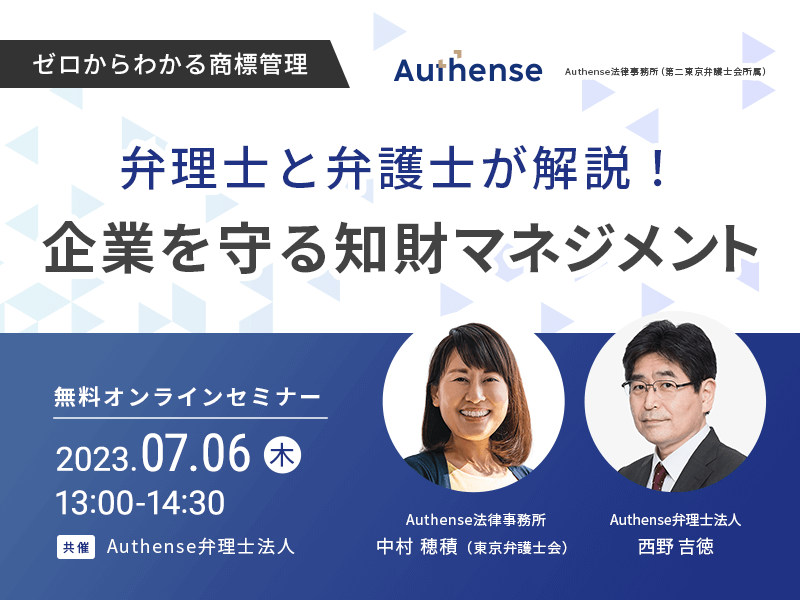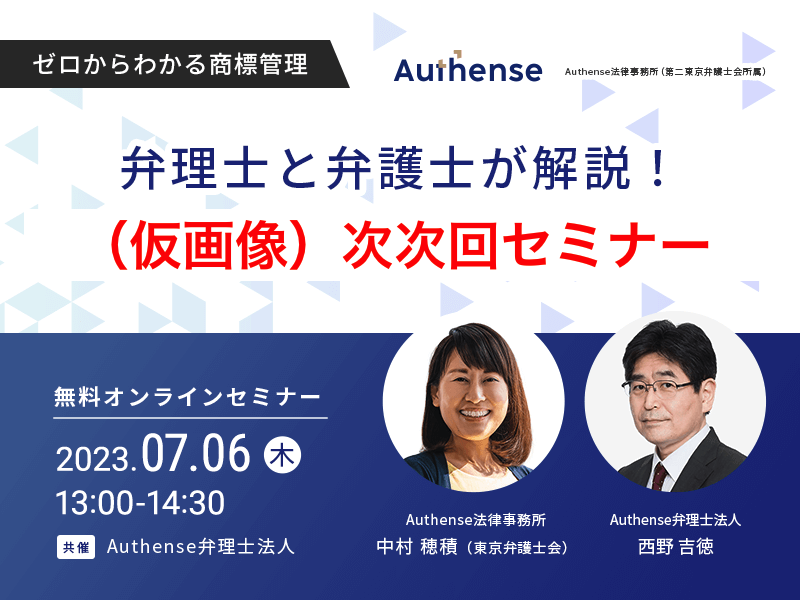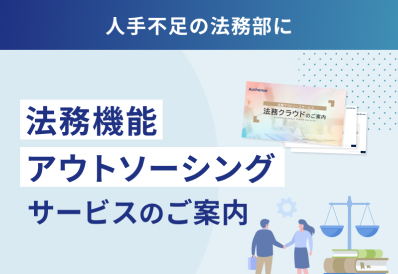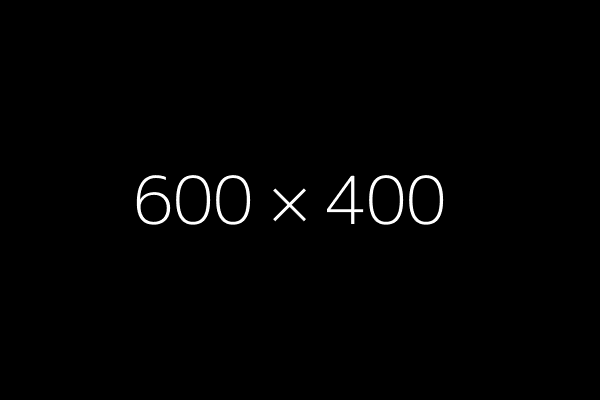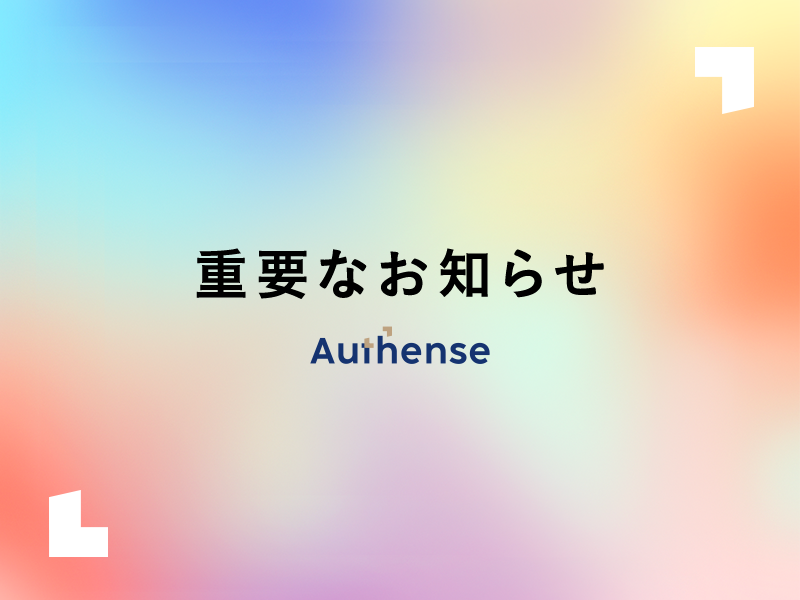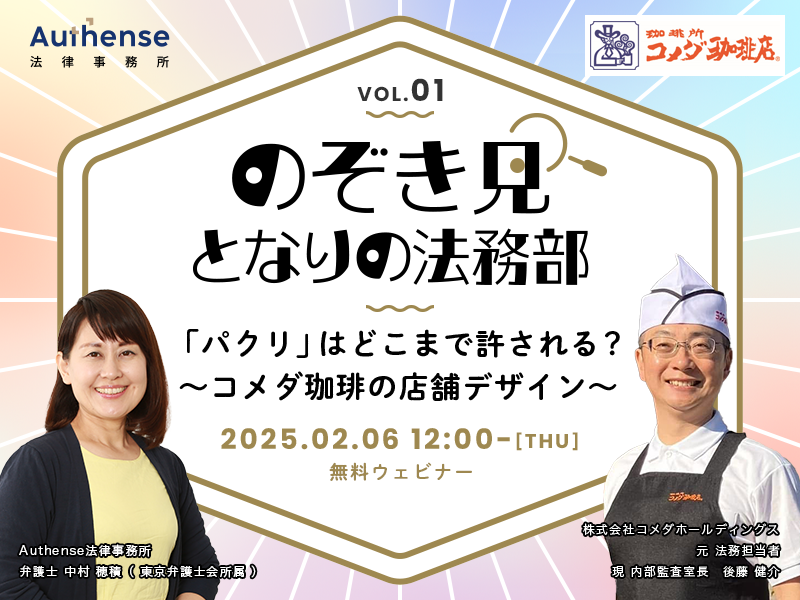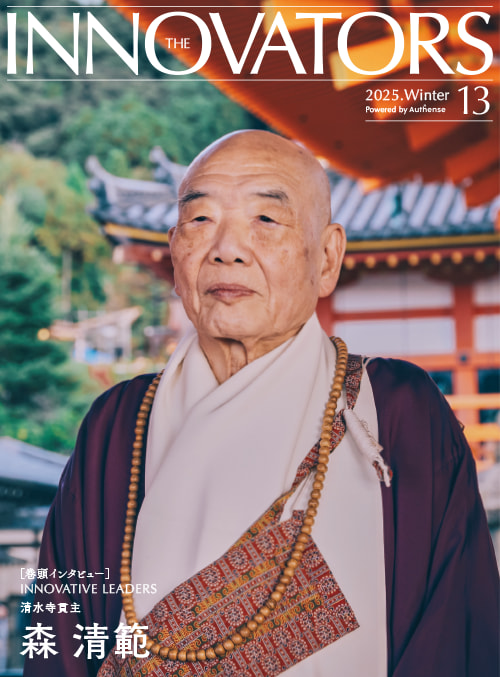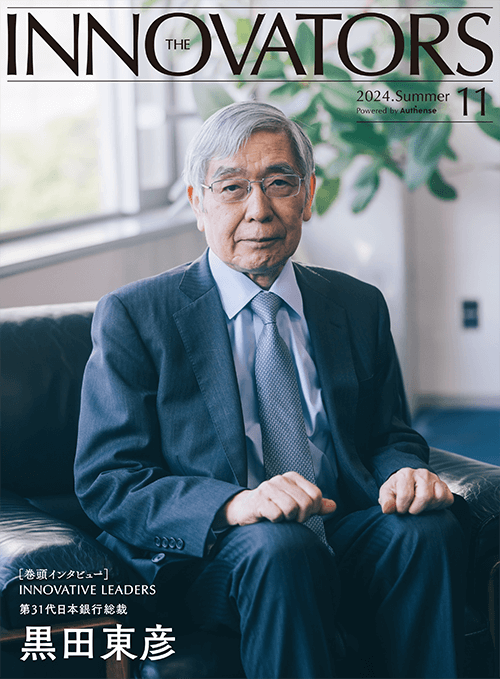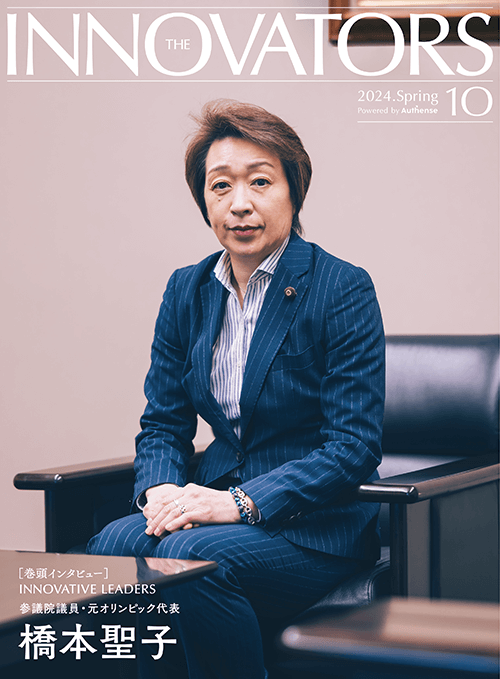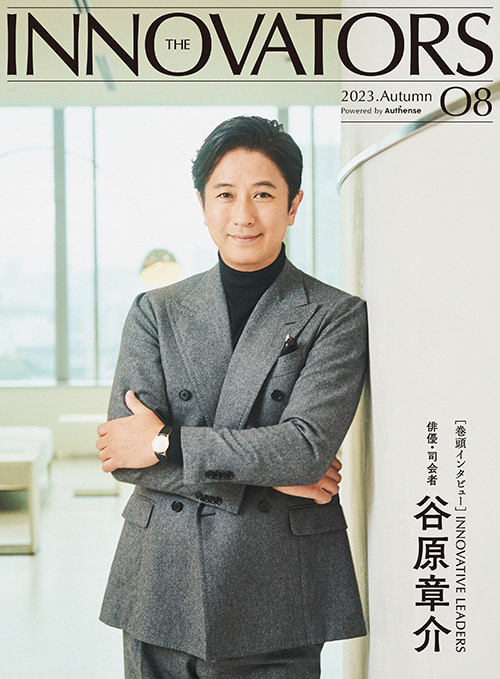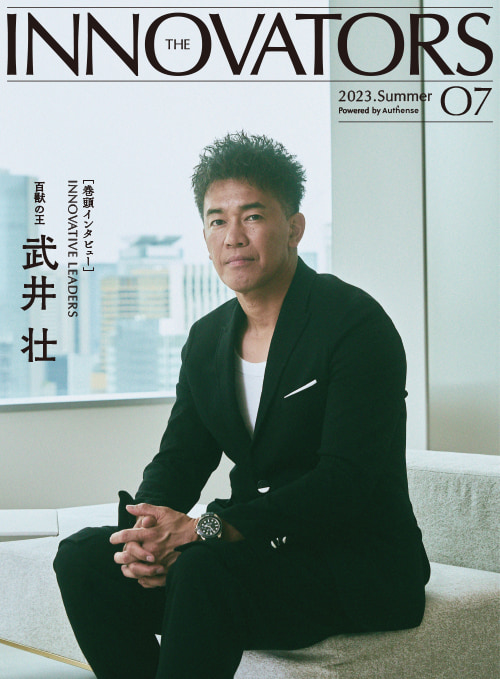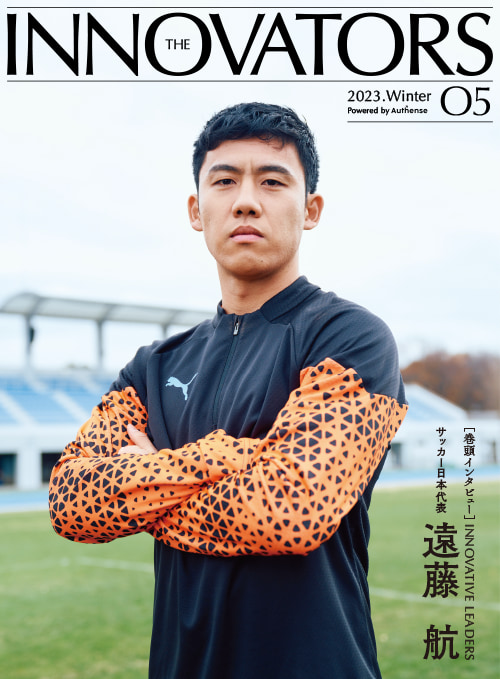電気事業を営む事業者は、電気事業法を十分に理解しておかなければなりません。
では、電気事業法とはどのような法律なのでしょうか?
また、電気事業法に違反した場合、どのような罰則の対象となるのでしょうか?
今回は、電気事業法の概要や2023年3月に施行された改正の概要、違反時の罰則などについて弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
電気事業法とは
電気事業法とは、電気事業の運営を適正かつ合理的とすることや、電気工作物の工事、維持及び運用に関する規制などを定めた法律です。
これにより、電気の使用者の利益保護や電気事業の健全な発達、公共の安全確保、環境保全などを図ることを目的としています(電気事業法1条)。
電気事業法で知っておくべき主な用語
電気事業法を読み解く前に、少なくとも次の3つの用語を理解しておく必要があります。
- 電気事業
- 電気事業者
- 電気工作物
ここでは、それぞれの概要を解説します。
電気事業
「電気事業」とは、次の事業を指します(同2条1項16号)。
- 小売電気事業:一般の需要に応じて電気を供給する「小売供給」を行う事業(2、5、6に該当する部分を除く)(同1号、2号)
- 一般送配電事業:自らが維持・運用する送電用・配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給と電力量調整供給を行う事業(6に該当する部分を除く)。その送電・配電用の電気工作物により、一定の小売供給を行う事業を含む(同8号)。
- 送電事業:自らが維持・運用する送電用の電気工作物により、一般送配電事業者または配電事業者に振替供給を行う事業(2に該当する部分を除く)のうち、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める一定の要件に該当するもの(同10号)。
- 配電事業:自らが維持・運用する配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給と電力量調整供給を行う事業(2と6に該当する部分を除く)のうち、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める一定の要件に該当するもの(同11号の2)。
- 特定送配電事業:自らが維持・運用する送電用・配電用の電気工作物により、特定の供給地点において小売供給・小売電気事業・一般送配電事業・配電事業を営む他の者に、その事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(6に該当する部分を除く)(同12号)。
- 発電事業:自らが維持・運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業・一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、または放電する事業のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める一定の要件に該当するもの(同14号)。
- 特定卸供給事業:特定卸供給(発電等用電気工作物を維持・運用する他の者に対して一定の方法により電気の供給能力を有する一定の者から集約した電気を、小売電気事業・一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業の用に供するための電気として供給すること)を行う事業でのうち、その供給能力が経済産業省令で定める一定の要件に該当するもの(同15号の2、15号)。
「電気事業」のなかにはこれらの事業が含まれるため、確認しておきましょう。
電気事業者
「電気事業者」とは、次の事業者を指します(同17号)。
- 小売電気事業者:小売電気事業を営むことについて経済産業大臣の登録の登録を受けた者(同3号)
- 一般送配電事業者:一般送配電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者(同9号)
- 送電事業者:送電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者(同11号)
- 配電事業者:配電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者(同11号の3)
- 特定送配電事業者:特定送配電事業を営むことについて経済産業大臣への届出をした者(同13号)
- 発電事業者:発電事業を営むことについて経済産業大臣への届出をした者(同15号)
- 特定卸供給事業者:特定卸供給事業を営むことについて経済産業大臣への届出をした者(同15号の4)
これらの事業を営むには、後ほど解説するとおり所定の登録・許可を受けたり届出をしたりしなければなりません。
適正な許可や登録、届出のもとで事業を営むこれらの事業者を、まとめて「電気事業者」といいます。
電気工作物
電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・配電・電気の使用のために設置する次のものなどを指します(同18号)。
- 機械
- 器具
- ダム
- 水路
- 貯水池
- 電線路
- その他の工作物(船舶、車両、航空機に設置されるものなど一定のものを除く)
電気事業法による主な許認可制度
電気事業法では、電気事業を営むための許認可制度について規定されています。
ここでは、登録対象の事業と許可対象の事業、届出対象の事業について、それぞれ概要を解説します。
登録対象の事業
登録とは、所定の要件を満たすことで事業を営むことが認められる制度です。
要件を満たすか否かの審査は存在するものの、行政庁側の裁量はほとんどありません。
電気事業法において登録対象とされている事業は次のとおりです。
- 小売電気事業
許可対象の事業
許可とは、所定の要件を満たしたうえで申請し、許可を受けることで事業を営めるようになる制度です。
登録と比較して、行政庁の裁量が認められます。
電気事業法において許可対象とされている事業は次のとおりです。
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 配電事業
- 特定供給
届出対象の事業
届出とは、所定の届出書類を提出することで事業を営めるようになる制度です。
単なる通知であることから、行政庁側に裁量はありません。
電気事業法で届出対象とされている事業は次のとおりです。
- 特定送配電事業
- 発電事業
- 特定卸供給事業
電気工作物に関する規制
電気事業法では、電気工作物に関しても規制がなされています。
ここでは、電気工作物に関する主な規制を2つ解説します。
一般用電気工作物に関する規制
一般電気工作物とは、次の工作物を指します。
- 600V以下で受電した電気を使用する電気工作物のうち、一定のもの
- 低出力の小規模発電事業(出力10kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の小水力発電設備など)
たとえば、一般家庭や商店、コンビニ、小規模事務所の分電盤や屋内配線などがこれに該当します。※1
経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める一定の技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者または占有者に対してその技術基準に適合するように次の措置を講じることが可能です(同56条)。
- 修理・改造・移転・使用の一時停止を命じる
- その使用を制限する
また、一般用電気工作物と電気的に直接接続する電線路を維持・運用する者(「電線路維持運用者」といいます)は、経済産業省令で定める一定の場合を除き、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければなりません(同57条1項)。
事業用電気工作物に関する規制
事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物です。
事業用電気工作物は、さらに「電気事業の用に供する電気工作物」と「自家用電気工作物」に区分されます。
いずれも一般電気工作物と比較して大規模なものが想定されており、より厳しい規制がなされています。
事業用電気工作物に関する主な規制は次のとおりです。
技術基準への適合の維持
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を所定の技術基準に適合するように維持しなければなりません(同39条)。
なお、この技術基準は次の内容で定めるべきとされています。
- 人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないようにすること
- 他の電気的設備その他の物件の機能に、電気的または磁気的な障害を与えないようにすること
- 事業用電気工作物の損壊により、一般送配電事業者または配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること
- 一般送配電事業または配電事業の用に供される場合には、その事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業または配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること
保安・主任技術者の設置
小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するため、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めたうえで、その組織における事業用電気工作物の使用の開始前に主務大臣に届け出なければなりません(同42条1項)。
また、事業用電気工作物の工事や維持、運用に関する保安の監督をさせるため、原則として主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければなりません(同43条)。
工事計画・検査
事業用電気工作物の設置・変更に関する一定の工事をしようとする者は、その工事の計画について、原則として主務大臣の認可を受ける必要があります(同47条)。
また、使用開始前の検査や定期検査なども受けなければなりません(同49条など)。
事業用電気工作物の承継
事業用電気工作物を設置する者について相続、合併、分割があった場合は、相続人や合併存続法人などは、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継するとされています。
地位を承継した者は遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなりません(同55条の2)。
【2023年3月施行】電気事業法の改正ポイント
電気事業法の改正法が、2023年3月に施行されています。
ここでは、改正の主なポイントについて解説します。
認定高度保安実施設置者に係る認定制度の導入
1つ目は、認定高度保安実施設置者に係る認定制度の導入です。
これは、「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」を国が認定する制度です。
認定を受けた事業者は、次の特例の対象となります。
- 保安規程の記録保存について、届出が省略できる
- 主任技術者選解任の記録保存について、届出が省略できる
- 定期自主検査の実施時期の柔軟化が可能となる
- 使用前・定期の安全管理審査を省略できる
小規模事業用電気工作物に係る届出制度等の導入
2つ目は、小規模事業用電気工作物に係る届出制度等の導入です。
これは、小規模な再エネ発電設備(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)を「小規模事業用電気工作物」に分類し、一定の規制委の対象とする制度です。
該当する場合には、次の規制の対象となります。
- 技術基準適合維持義務
- 基礎情報の届出
- 使用前自己確認結果の届出
登録適合性確認機関による事前確認制度の導入
3つ目は、登録適合性確認機関による事前確認制度の導入です。
これは、登録適合性確認機関が工事計画届出を事前に確認する制度です。
当面は風力発電設備のみ対象となります。
登録適合性確認期間は、現地の風条件や運転条件を踏まえつつ、設備設計の妥当性を確認します。
電気事業法に違反するとどうなる?
電気事業法に違反すると、どのような措置の対象となるのでしょうか?
最後に、違反時の罰則などについて解説します。
技術基準適合命令の対象となる
事業用電気工作物が技術基準省令で定める技術基準に適合していない場合、経済産業大臣からその電気工作物の修理や改造、移転、使用の一時停止が命じられたり、使用を制限されたりする可能性があります(同40条、56条)。
これに違反した場合には、刑事罰の適用対象となります。
登録や許可が取り消される
電気事業法に違反した場合、登録や許可が取り消される可能性が生じます(同2条の9など)。
許可や登録が取り消されればその事業を継続することができなくなり、多大な影響が及ぶことでしょう。
刑事罰の対象となる
電気事業法に違反した場合、刑事罰の適用対象となります。
たとえば、許可が必要な電気事業を無許可で営んだ場合の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です(同116条)。
また、登録を受けることなく登録の必要な電気事業を営んだ場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(同117条の2)。
さらに、法人の業務の一環として違反がなされた場合には、行為者が罰せられるほか、法人も数億円単位の罰金刑の対象となる可能性があります(同121条)。
違反することのないよう、電気事業法の内容を正しく理解しておきましょう。
まとめ
電気事業法の概要や主な規制内容などについて解説しました。
電気事業法とは、電気事業の適正運営や電気工作物の工事・維持などについて定めた法律です。
電気事業法に規定される電気事業を営む事業者や、電気工作物の設置などに携わる事業者は、この法律を十分理解しておく必要があります。
違反した場合には、登録や許可が取り消されるほか、刑事罰が課される可能性もあります。
万が一にも違反することのないよう、電気事業法の内容をよく理解したうえで、判断に迷う際には弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所は、企業法務に特化した専門チームを設けており、電気事業法に関するリーガルサポートも行っています。
電気事業法についても相談できる弁護士をお探しの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。