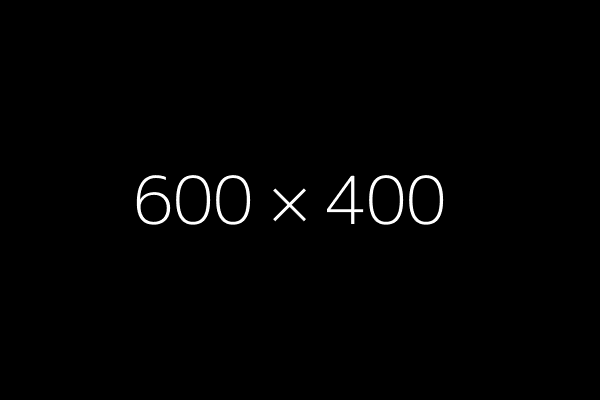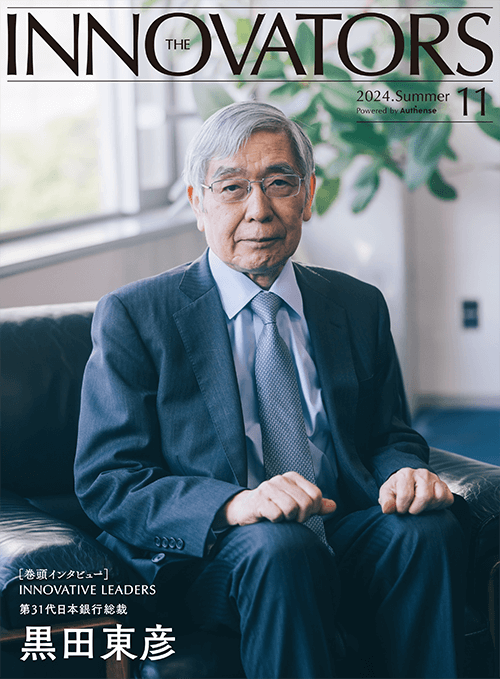昨今、日本においてeスポーツが盛んに行われつつあります。直近では、日本野球機構が任天堂の「スプラトゥーン2」を採用したeスポーツリーグを開催することが発表されました。既に海外ではeスポーツは非常に大きな市場となっており、今後日本でも大きな市場が形成されていくことが期待されます。
日本においては、賞金制の大会を開催するにあたっては、刑法・景品表示法・風営法による法的規制のため開催が困難とされていました。今回は、現段階での議論の状況をまとめていきます。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
1. 刑法 賭博罪(刑法185条)の該当可能性
まず、eスポーツの賞金制大会において賭博罪の適用可能性が問題になります。
刑法上の「賭博」とは、「偶然の勝敗により、財物・財産上の利益の得喪を争うこと」とされています。
ポイントとなるのは、以下の3点です。
①偶然の要素に左右されること
②財物・財産上の利益についてのものであること
③獲得・喪失を参加者同士で争うこと
判例上、囲碁や将棋といった偶然が入り込みにくい競技においても、偶然性が認められています。したがって、eスポーツは原則として①を満たすといえ、多くの賞金制大会では②も満たすことになるでしょう。仮想通貨も、改正資金決済法上「準通貨」として規定されていることから、②を満たします。
したがって、重要となるのは③獲得・喪失を参加者同士で争うこととなります。
参加者間において、財物等の獲得と喪失の相互関係がある場合には当該要件に該当してしまいます。例えば、参加者から参加費を徴収し、参加費を大会勝者に分配する場合には、敗者と勝者に財物の獲得・喪失関係が生まれてしまいますので、当該要件に該当してしまいます。
一方で、第三者が賞金を準備する場合には財物の獲得・喪失関係は生まれませんので、賭博罪は成立しません。例えば、スポンサーが賞金を準備する場合や、参加者と観戦者を明確に区別し、参加者からは費用を徴収せず、観戦者に対してのみ入場料を徴収する形の場合であれば賭博罪が成立しないと考えられます。
2. 景品表示法の該当可能性
(1) 景品類の該当性
賞金制のeスポーツは、ゲームという「特定の行為の優劣」によって賞金を得る者を決定します。この賞金が、景品表示法にいう「景品類」に該当する場合、賞金制のeスポーツは、公正取引委員会のいわゆる「懸賞制限告示」に定める「懸賞」に該当することになり、賞金の最高額は、①懸賞にかかる取引の価額の20倍、②①の金額が10万円を超える場合は、10万円を超えてはならないという規制を受けます。なお、賭博罪の項で述べたとおり、偶然性が入り込みにくい競技でも偶然性が認められておりますが、偶然性を利用して賞金を得る者を決定する場合でも、結論は変わりません。
たとえば、仮に景品表示法の適用がある場合には、販売価格が5000円を超えるゲームソフトの販売に、景品の上限額は10万円と定められることとなります。
そこで、賞金が「景品類」に該当するかどうかが問題となります。
景品表示法における「景品類」(景品表示法第2条3項)とは、以下のものを指します。
①顧客を誘引するための手段として
②事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する
③物品、金銭などの経済上の利益
残念ながら、2016年に行われた法令適用事前確認手続(いわゆるノーアクションレター制度)に対する消費者庁の回答をもとにすると、プレイするたびに料金がかかるアーケードゲーム、プレイするために購入が必要なコンシューマーゲームやPCゲーム、課金することにより有利となるタイプの課金制のゲームは、ゲーム会社が賞金を提供する場合、①顧客を誘引するための手段、そして②取引に付随して提供されるものとの要件に該当してしまうと解されます。これは、たとえばコンシューマーゲームやPCゲームの場合、これらを購入してやり込んだプレイヤーがどうしても有利になり、そのようなやり込んだプレイヤー以外が成績優秀者として賞金を獲得する可能性は低いという点が背景にあります。すなわち、コンシューマーゲームやPCゲームの購入を「取引」とみて、賞金はその「取引」に付随するものであるとして、「景品類」に当たると考えられます。
したがって、現在市場に出回っているゲームの多くは、ゲーム会社が賞金提供を行う場合には、その賞金は「景品類」に該当してしまうと解されます。この場合、賞金額の上限は、10万円を上限として、ゲームの販売価格の20倍までということになります。
一方で、第三者が賞金を準備する場合には②事業者が自己の供給する商品に付随して相手方に賞金を提供するとは言えないため、景品表示法の規制を受けないと解されます。ゲームセンターが賞金を準備する場合などが考えられますが、後述する風営法による規制が問題となってしまいます。
ところで、ここまでコンシューマーゲームやPCゲームを例に挙げてきましたが、課金制ゲームの場合、「課金することにより有利になる」かどうかの判断は非常に難しいと考えられます。もちろん、基本プレイが無料で、かつ課金によっても有利となり得ないゲームであれば、そもそも「取引」がありませんので、賞金も「景品類」に当たらないと考えられます。消費者庁も、上述の回答の中で、「課金型ゲームでは課金した者が有利になる」と判断しているわけではありません。そのため、個々のゲームごとに判断する必要があります。
たとえば、強力なキャラクターやアイテムを課金なしで入手できる可能性や確率、ゲームのプレイ時間をアイテムで伸ばすことのできるゲーム(いわゆる行動ポイント型)において、そのアイテムを課金なしで入手できる可能性や確率、さらには、そもそもプレイ時間を伸ばすことにより有利となるか否か、といった要素を考慮することになるでしょう。
(2) 役務の提供
一方で、取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供にあたらない、とされています(「平成26年12月1日付景品類等の指定の告示の運用基準について」5⑶)。したがって、「仕事の報酬等」として解釈できる賞金の提供については、景品表示法の規制を受けません。冒頭で述べた日本野球機構によるリーグ戦は、あらかじめ参加者を限定することで各選手に対し契約を締結し、試合を行うという「仕事の報酬」として賞金の支払を行っているものと考えられます。また、昨年eスポーツの統一団体として設立されたJeSUは、プロライセンス制度の導入を目指すことを表明しています。大会賞金を、プロゲーマーのパフォーマンスに対する「仕事の報酬」とすることで景品表示法の規制を乗り越える試みと考えられますが、仕事の報酬とすることで青天井に賞金を設定することが可能なのか、そもそもプロライセンス制度が必要なのか等、いまだ法的議論が継続しています。
3. 風営法の該当可能性
eスポーツの大会は、風営法上のいわゆるゲームセンター営業に該当し、風営法上の規制が及ぶ可能性があります(風営法2条5号)。
風営法上ゲームセンター営業にあたるものは、以下の場合です。
①スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える
②店舗その他これに類する区画された施設において
③当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業にあたる場合
そして、風営法上のゲームセンター営業に該当する場合には、管轄の都道府県公安委員会に許可を受ける必要があるほか、その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない(同23条2項)、とされています。
そのため、ゲームセンター営業において、ゲームセンター側が主体となって賞金制の大会を行うことは原則として「遊戯の結果に応じて賞品を提供する」ことになり認められません。
一方で、イベント会場などにおいて賞金制の大会を行うことについては、未だ議論が固まっていません。
例えば、ゲーム機及びPCゲーム用のコンピュータを会場に複数設置する場合について検討します。平成30年1月30日付風営法解釈運用基準において、風営法上の①テレビゲーム機は、勝敗を争うことを目的とする遊戯をさせる機能を有するものを含むことが示されています。ゲーム機及びゲームができるコンピュータは、いずれも当該機能を有すると解されるため、これを満たすと考えられます。
一方で、②店舗③営業についてはイベントごとに個別具体的に判断されることとなり、明確といえる判断基準は現在のところ存在していません。特に③営業に関しては、反復継続の意思がある場合には、1回のみの開催であっても「営業」とみなされることがあり注意が必要となります。警察庁より早急に解釈基準が示されることが望まれますが、現在は各都道府県公安委員会の判断にゆだねられています。
4. おわりに
賞金制のeスポーツ大会に関し、現在の議論の状況を簡単に整理いたしました。風営法に関するeスポーツ大会の適用の可否については今後の警察庁の判断基準次第とはなりますが、風営法上のゲームセンター営業にあたらない場合において、適法に開催できる賞金制大会として例えば以下の大会形式が考えられます(筆者私見)。
①主催者がゲーム会社とは別であり、スポンサーが賞金を拠出する大会
②主催者がゲーム会社とは別であり、参加料を取らず観戦料で賞金を拠出する大会
③出場者を限定する等により、仕事の報酬として賞金を拠出する大会(但し報酬と認められる金額に限る)
実際に賞金制のeスポーツ大会を開催する場合には、現段階では、事前に所轄の公安委員会及び消費者庁に問い合わせを行うことが必要であるといえます。未だ法的議論は継続していますが、eスポーツの発展のためには、早急に各法律上の解釈の統一、解釈基準の公表が行われることが不可欠といえるでしょう。
(※本原稿は、平成31年3月1日時点のものです。)