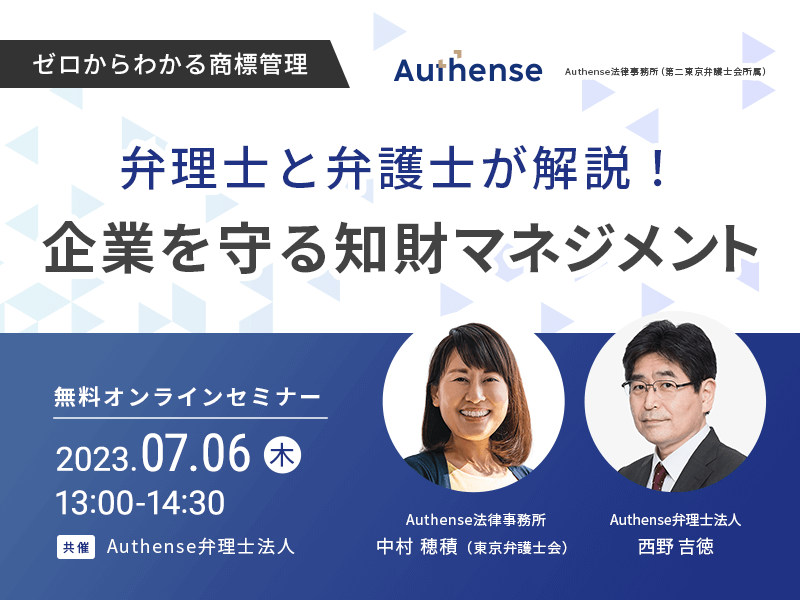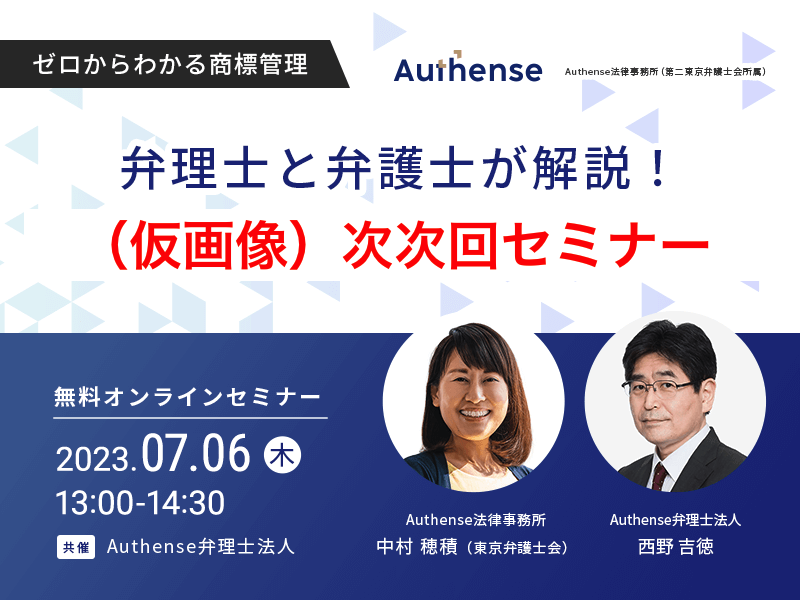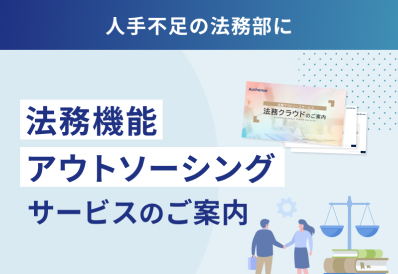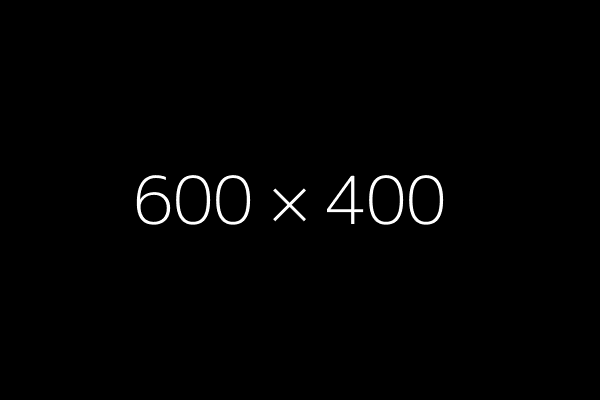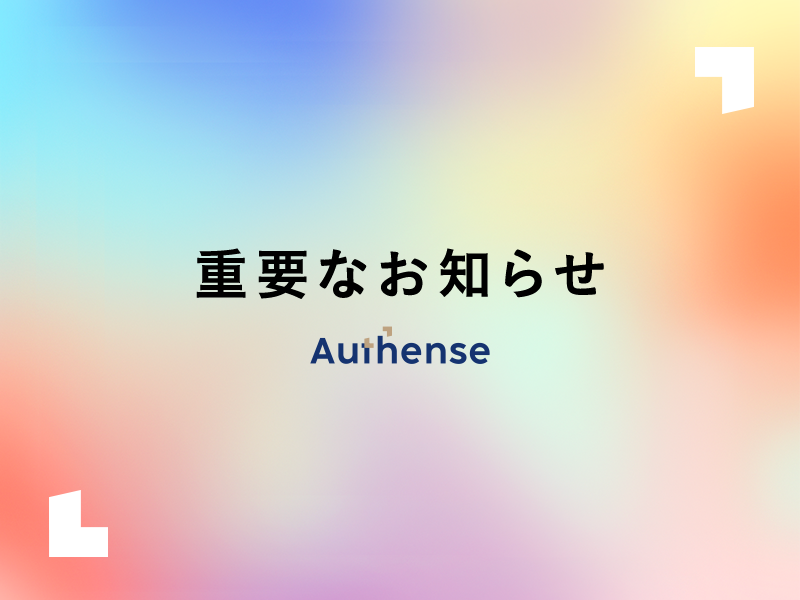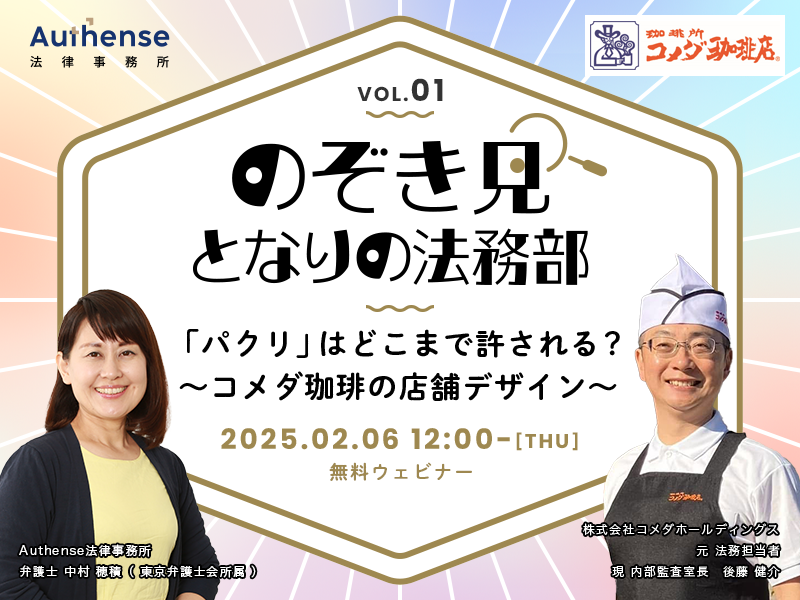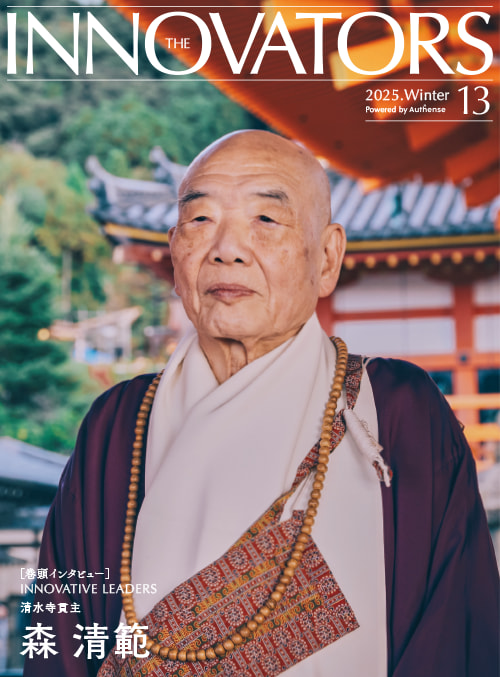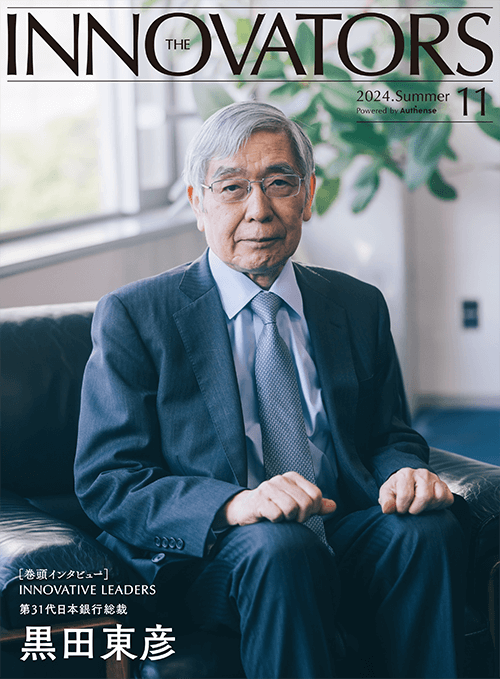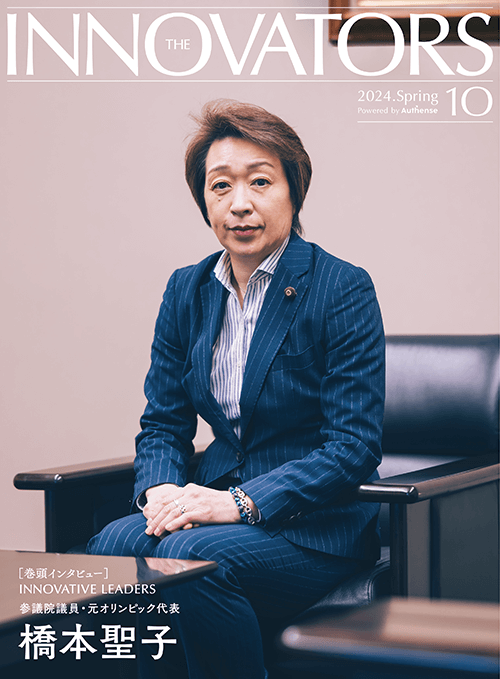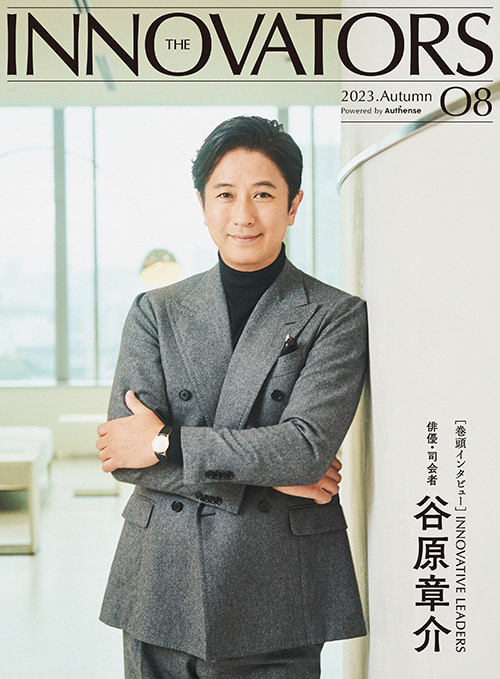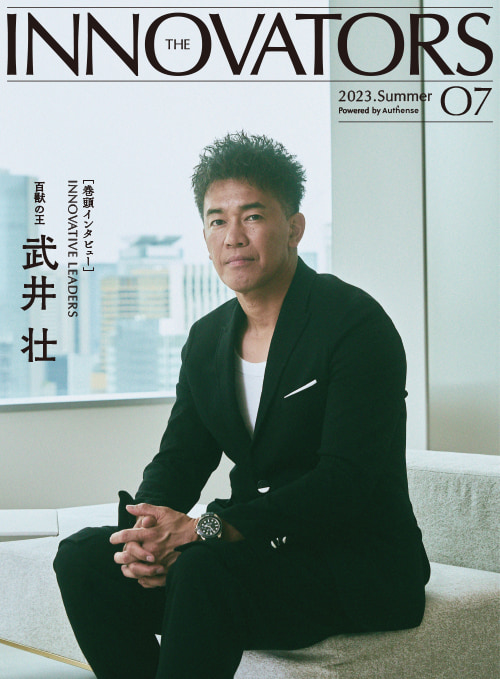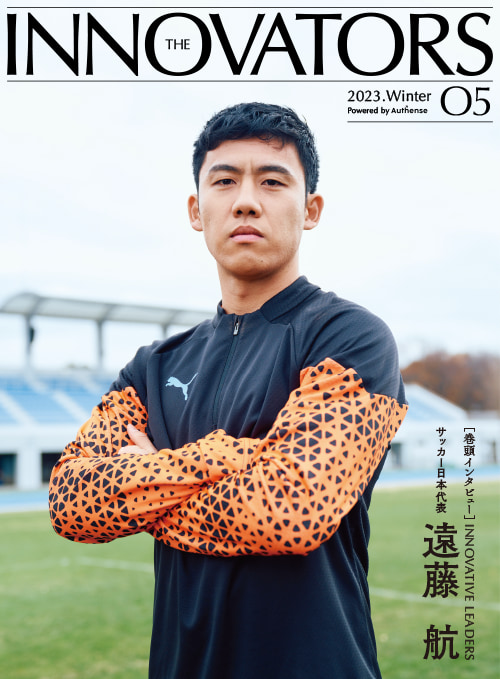インターネットへの書き込みなどを発端として、企業が風評被害に遭う場合があります。
風評被害に遭ったら、どのように対処すればよいのでしょうか?
また、風評被害の発端となった書き込みに対しては、どのような法的措置が検討できるのでしょうか?
今回は、風評被害の概要や対処法などについて、弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
風評被害とは
風評被害について、法律の定義はありません。
一般的には、根拠のない虚偽の情報や不確かな情報が拡散されることにより、企業や製品などの信用が損なわれることを指します。
たとえば、事実ではないにもかかわらず「A社が製造した食品から虫が出てきた」、「A社が製造した食品を食べたら食中毒になった」という情報がSNSに投稿されこれが拡散されることで、A社の業績が悪化する場合などがこれに該当します。
また、科学的根拠が十分でないにも関わらず「Bという成分が身体に悪い可能性がある」などと報道された結果、Bを使った製品の売上が低迷する場合なども風評被害といえるでしょう。
同様に、コロナ禍などの感染症蔓延時には、「C店に感染者が出入りした」など真偽不明の情報が拡散され、客足が途絶えるケースもあります。
風評被害は、どの企業にとっても他人事ではありません。
風評被害に遭った際は早期に適切な対応をすることで、被害を最小限に食い止められる可能性が高くなります。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
風評被害が発生する主な原因
風評被害は、どのような原因で発生するのでしょうか?
ここでは、主な原因を3つ紹介します。
- インターネット上へのネガティブな書き込み
- マスメディアの偏向報道
- 誤解を招くデータやグラフ
なお、これらの原因のうち1つだけが原因となる場合もあれば、複数の原因が組み合わさって風評被害が生じることも少なくありません。
たとえば、誤解を招くデータやグラフを見つけた人が誤解したままこれをSNSに投稿し、拡散されるケースなどがこれに該当します。
インターネット上へのネガティブな書き込み
1つ目は、インターネットへのネガティブな書き込みです。
特にSNSは拡散力が高く、風評被害の影響が大きくなりやすいといえます。
インターネットへのネガティブな書き込みは、投稿者の誤解である場合も少なくありません。
一方で、誤った正義感などから企業への攻撃を目的として投稿するケースや、いわゆる「バズり」を目的として過激な投稿をするケースもあります。
マスメディアの偏向報道
2つ目は、マスメディアの偏向報道です。
マスメディアの影響は今も強く、テレビや雑誌などが偏った内容で報道した場合、これが風評被害の原因となることがあります。
特に、東日本大震災の際の放射能にまつわる報道では、対象地域の農産物や海産物を中心に多くの風評被害が生じました。
誤解を招くデータやグラフ
3つ目は、誤解を招くデータやグラフです。
データやグラフは一見正確なようでも、切り取り方や目盛の振り方などによって異なる印象を与えやすいものです。
また、何らかの主張をしたい人によって、自身の主張を裏付けるために、前提条件などを無視した状態でデータやグラフが引用されることもあります。
その結果、誤った認識や過大な認識などにより、風評被害が生じる場合があります。
風評被害が企業に及ぼす主な影響
自社が風評被害に遭った場合、企業にはどのような影響が及ぶ可能性があるのでしょうか?
ここでは、主な影響について解説します。
- 売上の低下
- 人材採用の難航・従業員の退職
- 取引先の離反
- 株価の低迷
- 問い合わせや嫌がらせへの対応
風評被害に遭ってお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所は、企業法務に特化した専門チームを設けており、風評被害にまつわるご相談についても多くの対応実績があります。
売上の低下
風評被害に遭った場合、売上が低下するおそれが生じます。
流布された内容を信じた人が、自社製品の購入や来店などを控える可能性があるためです。
また、拡散が止まってからも流布された内容の印象が残り、「何となく」購入や来店が控えられるおそれもあります。
人材採用の難航・従業員の退職
風評被害に遭った場合、人材採用が難航するおそれが生じます。
風評被害は、たとえ根も葉もない内容であってもその印象が残ることがあり、流布された内容によっては求職者から忌避される場合があるためです。
また、流布された内容が従業員の印象をも低下させる内容である場合、従業員が退職するおそれも生じます。
さらに、流布された内容に関する連日の問い合わせや店頭でのクレームなどに疲弊し、退職する場合もあるでしょう。
取引先の離反
風評被害に遭った場合、取引先が離反するおそれが生じます。
流布された内容によっては取引先などにまで影響が及ぶ可能性があり、取引先としてもリスクヘッジの必要があるためです。
株価の低迷
風評被害に遭った企業が上場企業である場合、株価の低迷につながる可能性があります。
株価の低迷は、流布された内容を株主が信じていることによって起きる場合もあれば、「流布された内容は虚偽である可能性が高いものの、これを信じている人が一定数いる以上は売り上げが低迷するだろう」と株主が判断することによって起きる場合もあります。
問い合わせや嫌がらせへの対応
流布された内容によっては、企業に対して問い合わせや嫌がらせの連絡が殺到する可能性があります。
その結果、電話回線の不足や人手の不足により本来受けたい連絡に対応できず、業務が滞るおそれが生じます。
また、店舗がある場合は、店舗スタッフが流布された内容について頻繁に質問されるなどして、対応に苦慮する事態ともなり得るでしょう。
近年では、インターネット上で「悪ふざけ」のような嫌がらせがされるケースも散見されます。
たとえば、Google Map(グーグルマップ)の情報が無断で書き換えられたり、口コミが荒らされたりすることなどが想定されます。
風評被害に遭った場合の主な対応
風評被害に遭った場合、企業はどのように対策をすればよいのでしょうか?
ここでは、主な対処法について解説します。
- 弁護士へ相談する
- 声明文を出す
- 警察などの公的機関へ相談する
弁護士へ相談する
風評被害に遭った場合は、早期に弁護士へご相談ください。
風評被害の状況や適切な対処法は状況によって異なるため、早期に弁護士へ相談することで、そのケースにおける適切な対処法を把握しやすくなるためです。
Authense法律事務所は企業法務に特化したチームを設けており、風評被害に遭った際の対策に関するご相談も可能です。
風評被害でお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
声明文を出す
風評被害に遭った場合、早期に声明文を出しましょう。
企業に関するよくない噂を目にした場合、多くの人は半信半疑です。
企業が公式に声明文を出すことで根も葉もない噂であることが明確となり、信用の回復につながります。
なお、企業がせっかく声明文を出しても、ひっそりと公式ホームページに掲載しただけでは気付いてもらうことができず、風評被害が続くおそれがあります。
そのため、風評被害の出処がSNSの場合はSNSにも声明文を掲載し、多くの人の目に留まるよう工夫するとよいでしょう。
企業が声明文を出す際は、表現などに注意が必要です。
風評被害に遭っている場合は企業に注目が集まっており、表現に問題があると火に油を注ぐ事態となりかねないためです。
企業側にも多少なりとも非がある場合には、特に注意しなければなりません。
そのため、声明文を公表する前に、外部の弁護士に客観的な視点で確認を受けることをおすすめします。
警察などの公的機関へ相談する
風評被害の内容によっては、公的機関に相談することも対策の1つです。
具体的には、次の窓口などへの相談が検討できます。
- 警察庁の「サイバー事案に関する相談窓口」
- 総務省から委託されている「違法・有害情報相談センター」
相談先の窓口についても、弁護士へ相談したうえで検討するとよいでしょう。
風評被害の原因となったインターネット上の書き込みに対して検討できる法的措置
SNSなどインターネットへの書き込みが発端となり風評被害が起きている場合、発信元となった相手に対する法的措置が検討できます。
最後に、風評被害の原因となった書き込みをした者に講じられる法的措置について解説します。
- 開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
なお、これらはいずれか1つを選ぶようなものではありません。
まず、開示請求は損害賠償請求や刑事告訴の前段階として行うものです。
また、損害賠償請求と刑事告訴は、それぞれの要件を満たす限り、両方の措置を講じることもできます。
相手に講じる法的措置の内容でお困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
風評被害の状況や書き込みの内容などに応じて、適切な法的措置のメニューを提案します。
開示請求
開示請求とは、風評被害の原因となった書き込みをした者を特定する手続きです。
損害賠償請求をするためには、その前提として相手の身元が判明していなければなりません。
また、刑事告訴では相手の特定は要件ではないものの、あらかじめ相手が特定できているとスムーズです。
そのため、これらの法的措置に先立って、投稿者の身元を調べる開示請求をすることとなります。
開示請求は一般的に、次の2段階で行います。
- 投稿の舞台となったSNSの運営者(Xを運営するX Corp.など)やインターネット掲示板の管理者などに開示を求め、投稿のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手する
- 「1」で入手した情報をもとに、投稿者が接続に用いたプロバイダ(NTTやSoftbankなど)に契約者の住所や氏名などの開示を求め、これらの情報を入手する
とはいえ、SNSの運営者や接続プロバイダなどに対して直接情報の開示を求めても、開示に応じる可能性はほとんどありません。
そのため、開示請求や裁判手続によって行うことが一般的です。
なお、開示請求の根拠であるプロバイダ制限責任法が改正されたことにより、「1」と「2」の手続きを一括して行える「発信者情報開示命令」が創設されました。
これにより、開示請求の一本化と短期化が可能となっています。
しかし、これは非訟事件であり、活用にはデメリットもあります。
従来の「発信者情報開示請求」の方が適している場合もあるため、弁護士へ相談したうえで適切な手続きを選択してください。
損害賠償請求
損害賠償請求とは、相手の不法行為(風評被害の原因となった虚偽の情報などの投稿)によって生じた損害を、金銭の支払いで償うよう求めることです。
適正な請求額は、書き込まれた内容やこれにより企業に生じた損害の内容によって大きく異なります。
企業の業績に影響が及んだ場合には、多額の損害賠償請求が認められる可能性があります。
そのため、まずは弁護士へ相談したうえでそのケースにおける適正額を把握するとよいでしょう。
損害賠償請求は、まず弁護士から相手に内容証明郵便を送るなどして行うことが一般的です。
この段階で相手が請求額を支払えば、事件は解決となります。
一方で、相手が請求に応じないなど、不誠実な対応をする場合は裁判を申し立て、裁判上での請求に移行します。
裁判で請求が認容され、これが確定したにもかかわらず、期日までに相手が賠償金を支払わない場合には、強制執行の対象となります。
刑事告訴
刑事告訴とは、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
インターネット上に企業の信用を毀損する情報の書き込む行為は、刑法上の名誉毀損罪や業務妨害罪に当たる可能性があります。
名誉毀損罪は、起訴をするために被害者側の告訴が必要となる親告罪であるため、告訴をしなければ相手を罪に問うことはできません。
また、業務妨害罪であっても捜査機関が独自に捜査をすることは稀であり、相手を罪に問うには告訴することが近道でしょう。
告訴が受理されると警察で捜査がなされ、必要に応じて相手が逮捕されます。
その後は相手の身元が検察に送られ、検察でも捜査がなされた結果、起訴か不起訴(刑事裁判を開始せず、事実上の無罪放免とすること)かが決まります。
起訴がされると刑事裁判が開始され、有罪・無罪や具体的な量刑が決まるという流れです。
まとめ
風評被害の概要や風評被害が企業に及ぼす影響を解説するとともに、風評被害の対処法などを解説しました。
企業が風評被害に遭うと、売上が低迷したり取引先が離反したりするリスクが生じます。
風評被害に遭ってしまったら、被害を最小限に抑えるために早期に弁護士へ相談し、声明文を出すなどの対応をとるようにしてください。
悪質である場合には、損害賠償請求などの法的措置も検討できます。
Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、風評被害にまつわるご相談についても多くの対応実績があります。
風評被害に遭いお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。