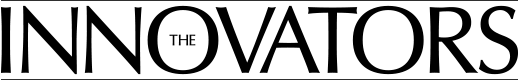1200年以上の歴史を誇る、京都・清水寺。折からのインバウンド・ブームの影響もあり、近年の年間参拝者数は500万人に達している。その裏側には、1988年の貫主就任以来、清水寺の顔として布教を続ける、森清範貫主の地道な活動と未来への熱い想いがあった。日本を代表する文化遺産を守り、育てていくためにどのようなことを考えてきたのか。話を伺った。
取材/元榮太一郎(本誌発行人) Taichiro Motoe・山口和史(本誌編集長) Kazushi Yamaguchi
文/山口和史 Kazushi Yamaguchi 写真/西田周平 Shuhei Nishida
「都が向こうからやってきた」。清水寺の長い歴史
- 観測史上、もっとも暑い夏となった2024年。その影響もあってか、11月下旬となってようやく色鮮やかな紅葉が伽藍を彩っていた。
森 清範 氏 (以下 森氏): 例年よりは遅いかもしれませんが、もうぼちぼち12月ですからね、例年なら散る時期でしょうけれども、紅葉はいまが見頃になっていますね。
- そう語るのは、京都の名刹・清水寺の貫主を務める森清範師だ。
取材日当日、清水寺には国内外から多くの参拝客が訪れていた。清水寺の年間参拝客数は500万人を超えるという。東京ディスニーランドの年間来園者数(2024年3月期)がおよそ2750万人とされているのと比較すると、その数の凄みがよく分かる。
森氏: やはり外国人の方が増えました。特にアジアの方々は仏教に篤い信仰心を持っておられますので、本堂で鐘を叩いて礼拝をするというような姿をよく見かけます。
- 京都といえば日本を代表する古都として知られる。街全体がひとつの文化遺産であり、1000年以上の歴史を誇る。先祖代々京都に暮らす人と「先の戦争」と話をした場合、第二次世界大戦ではなく応仁の乱のことだったという笑い話があるが、清水寺の場合はさらにその上を行く。
奈良から長岡京へ、そして京都の平安京に都が移されたのは794年(延暦13年)。一方、清水寺が現在の位置に創建されたのは778年(宝亀9年)。「都が向こうからやってきた」、こう語れるだけの歴史を持つ寺院は、日本にもそうそう無い。歴史と伝統を肌で感じるために、清水寺には世界各国の要人も訪れる。森貫主は日本と海外の文化交流や友好関係の橋渡しの役割も担っている。
森氏: 以前、ヒラリー・クリントンさんがお見えになりました。清水の舞台を案内すると『なんときれいな』と感動されていたんです。観音さんの浄土の世界がこれなんですと、いろいろな話もしました。伝わったかどうかは分かりませんけどね(笑)
- 清水の舞台から飛び降りるという言葉がある。思い切った決断をする際の気持ちを表す慣用句として、現在でも広く用いられている。
森氏: 駐日大使のウォルター・F・モンデールさんがお越しになった際、日本人が思い切ったことをするときには、この清水の舞台から飛んだんですとお話したことがありました。舞台から飛ぶということは、観音様に見守られながら思い切った祈願をするということです。本当に飛んだんですからね。
でも、明治になって禁止令が出されて、それ以降『飛んだつもり』ということになったんじゃないかと思いますけどね。
- かつて、清水の舞台から実際に飛び降りて願掛けをした人たちの記録は『清水寺成就院日記』に残っている。これまでに236人が飛び降りており、生存率は約85%。舞台の先端部は地上からおよそ12メートルの高さにあるが、当時は舞台の下に生えていた木々と柔らかな土がクッションとなり、この高い生存率になったと専門家は語っている。
年間500万人が訪れる一大ランドマークに育てた「想い」
- 森貫主は1940年(昭和15年)に生まれ、15歳で先々代の清水寺貫主・大西良慶和上に弟子入りしている。
森氏: 私の祖父が清水寺の堂守をしていたんです。晩年、師匠が縁があるところから弟子を取ると。それを聞いた両親から『お前が行け』と。
- 入寺後、修行を続け1988年に清水寺の貫主に就任した。1200年以上の歴史を持つ、日本を代表する文化遺産を守る責任やプレッシャーは大きい。貫主就任後、森師は清水寺をより広く知らしめるため、そして教えをより多くの人々に教えるために大きな一手を打った。
森氏: 当時、私は40代でした。何もかも、さっぱり分からない状況でしたが、がんばっていかなければいけないという話をよくしていました。
清水寺の本尊である秘仏十一面千手観音立像は33年に一度、ご開帳されます。そこで、2000年のご開帳に合わせて清水寺展を全国各地で行うことにしました。
- 清水寺展は北海道から九州、沖縄まで全国津々浦々で開催され、大盛況となった。美術館や博物館だけではなく、地方の百貨店などでも開催し、清水寺の知名度拡大とともに布教にも大きな影響をもたらした。
森氏: 京都まで来なくても、清水寺の重宝類をお参りしていただけるようにしようと開催しました。テレビ局や新聞社にもお願いをして、講演会も開かせていただきました。ありがたいことに、清水寺にはどなたも一度は修学旅行で来ていただいているんですね。皆さん、清水寺のことはご存知ですので、それならとたくさんお越しいただきました
- 2000年のご開帳は9ヵ月間にわたって行われた。清水寺門前会とも協力し、さまざまな行事も催した。
森氏: 観音様の布教をするのにいろいろな行事をおよそ1年間にわたって行ったんです。いまではできませんね。いまやると言われたら、『勝手にやって、もう1年間もつかどうか分からしません』って言いますよ(笑)。私も若かったのでできたんです。
皆さんのご協力のおかげもあって、無事に春に始まり、夏の暑い時期から冬の寒い時期まで、四季を通じて皆さんに観音様のご縁を結んでいただく布教の機会を作っていただいのが、貫主になって手掛けた大きな行事でした
- 歴史と伝統の上にあぐらをかかない。一人でも多くの方々に観音様とのご縁を結んでもらおうと考える。その努力の結果、2000年当時はおよそ300万人だった年間参拝者数は、2024年現在、500万人にまで増加している。森貫主は、清水寺の長い歴史のなかでもっとも多い参拝者を招いている住職、ということになる。
森氏: 時代も時代ですのでね。変わるものは変わる。変わらないものは変わらない。不易流行ですね。観音様の教えは変えてはいけません。では、その教えを伝えるためには、いま、どうやったら受けるのか、皆さんに伝わっていくのかということは考えています。
でも、あんまり変わらないですけどね。人と人ですから、対面ですよ。私はいまも、日本各地からお誘いいただいて講話に行きます。聞き手がたとえ10人であろうが、100人であろうが、1000人であろうが一緒ですから、対面でお話しをしていると、言葉はないんですけどね、反応があるんです。その反応を見ながらお話しをして、変わるものと変わらないものがあるんだな、ということを思っています。