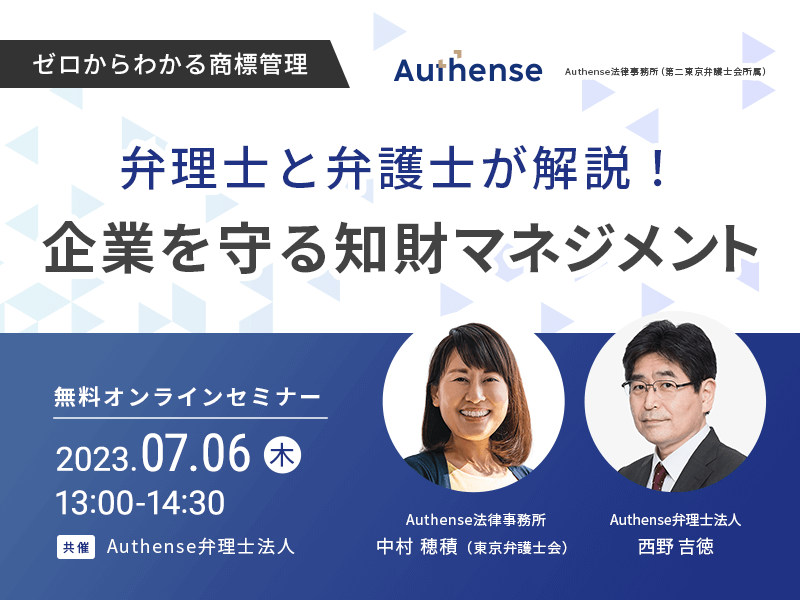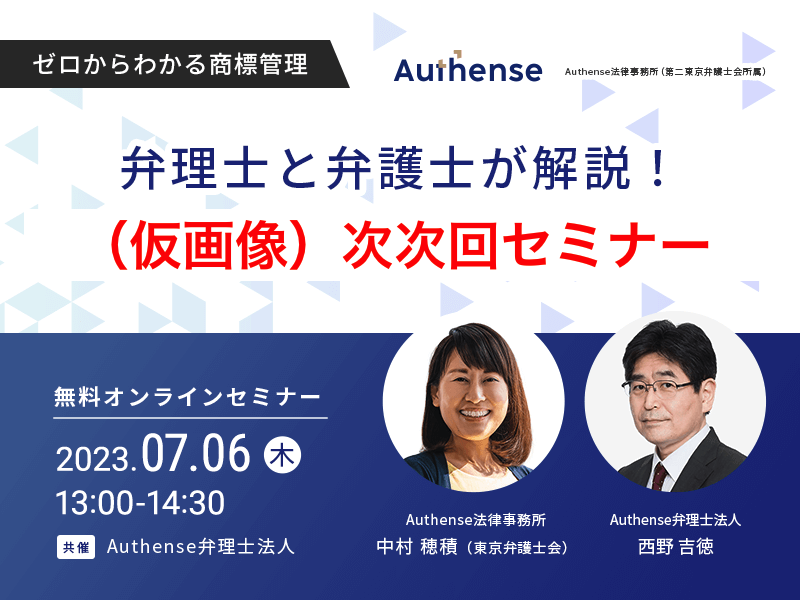人事評価制度は、多くの企業で導入されています。
しかし、人事評価制度は「流行りだから」などの理由で安易に導入すべきものではありません。
まずは自社の人事面での課題を把握したうえで、その課題解決に資する手段の1つとして人事評価制度の導入を検討すべきでしょう。
では、人事評価制度はどのような目的から導入されているのでしょうか?
また、人事評価制度の導入には、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
今回は、人事評価制度の目的や導入のデメリット、人事評価制度の導入目的を達成するポイントなどについて、社労士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)は人事評価制度の導入支援について豊富な実績を有しています。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
人事評価制度とは
人事評価制度とは、従業員の能力やスキルなどを適正に評価し、これを待遇や昇進などへ反映させる仕組みです。
ただし、人事評価制度は自社の状況や目的に合わせて設計する必要があり、決まったパッケージを採用すれば導入できるわけではありません。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
人事評価制度を構成する3つの要素
人事評価制度は、「等級制度」と「評価制度」、「報酬制度」の3つの要素から構成されています。
ここでは、それぞれの構成要素について概要を解説します。
等級制度
等級制度とは、各ポスト(等級)が求める役割や、その等級となるために満たすべき基準などを明確にする制度です。
等級制度を導入することで、従業員のキャリアパスが明確となるほか、希望するポスト(等級)に進むために現状として何が不足しているのかが明確となります。
評価制度
評価制度とは、個々の従業員を適切に評価するための制度です。
評価制度にはさまざまな手法が存在するため、自社に合った的確な評価制度を選択しなければなりません。
主な評価制度は、次のとおりです。
- 能力評価:業務上のスキルや素質を基準に評価するもの
- 成果評価:売上などの成果を基準に評価するもの
- 行動評価:経営理念・目標に沿った行動を評価するもの
- 情意評価:個々の従業員の内面を評価するもの
評価制度にはそれぞれ一長一短があるため、社労士へ相談したうえで自社に合った評価制度を選定しましょう。
お困りの際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください
報酬制度
報酬制度とは、給与・賞与などの待遇を決める制度です。
人事評価制度を導入する場合、等級や評価と連動させる形をとることが一般的です。
人事評価制度を導入する主な目的
人事評価制度は、どのような目的から導入されるのでしょうか?
ここでは、人事評価制度を導入する主な目的を5つ解説します。
自社にとっての目的を明確としたうえで導入を検討することで、課題達成に資する的確な人事評価制度の設計をしやすくなります。
- 企業のビジョンや方針を社内に浸透させること
- 公平な処遇を実現すること
- 効率的な人材育成を行うこと
- 人材の適正配置を実現すること
- 従業員のモチベーションを向上させ定着率を高めること
企業のビジョンや方針を社内に浸透させること
1つ目は、企業のビジョンや方針を社内に浸透させることです。
企業のビジョンや方針は、社内に掲示したり社長が年に数回話したりするだけで浸透するものではありません。
従業員にビジョンや方針を真の意味で浸透させるためには、自社のビジョンや方針に即した行動や考え方をした従業員を評価する仕組みが必要です。
人事評価制度を導入し、ビジョンや方針に即した行動を評価する設計とすることで、企業のビジョンや方針が社内に浸透しやすくなります。
公平な処遇を実現すること
2つ目は、公平な処遇を実現することです。
「頑張って会社に貢献しているにもかかわらず、大して貢献をしていない人と処遇がほとんど変わらない」という状況では、モチベーションが低下してしまいかねません。
また、ある従業員が「頑張っている」ことを上司もわかっていたとしても、これを評価に反映させる仕組みがなければ、処遇の改善は困難でしょう。
人事評価制度を導入して評価基準を適切に設定することで、自社にとって望ましい貢献をしている従業員を適切に評価することが可能となります。
これにより、「頑張っている人が適切に評価される」こととなり、公平感のある処遇を実現しやすくなるでしょう。
効率的な人材育成を行うこと
3つ目は、効率的な人材育成を行うことです。
人事評価制度を導入するにあたっては、従業員のキャリアアップのステップを描く必要が生じます。
具体的なキャリアパスは企業や職種によって異なるものの、たとえば、現在もっとも下位である1等級の従業員はこの後2等級、課長相当の3等級へと徐々にキャリアアップをして、4等級で部長相当になるというイメージです。
等級アップにあたっては、企業が定めた一定のスキル・能力などの要件を満たさなければなりません。
これにより、企業が「1等級の従業員を2等級へ上げるための研修」、「2等級の従業員を3等級へ上げるための研修」などより的確な研修が可能となり、効率的な人材育成が実現しやすくなります。
人材の適正配置を実現すること
4つ目は、人材の適正配置が実現しやすくなることです。
人事評価制度では、職種ごとに求められるスキルや能力を定めることが可能です。
これと、個々の従業員が達成したスキルや能力とを照らし合わせることで、人材の適正配置を実現しやすくなります。
従業員のモチベーションを向上させ定着率を高めること
5つ目は、従業員のモチベーションを向上させ、定着率を高めることです。
人事評価制度の導入によって公平な処遇が実現されることで、従業員のモチベーションが向上します。
また、等級を上げるために今の自分に不足している点が明確となることから、個々の従業員が取り組むべき努力の方向性が明確となり、これによってもモチベーションが向上するでしょう。
その結果、従業員の定着率が高まる効果が期待できます。
人事評価制度を導入するデメリット・注意点
人事評価制度は「導入さえすれば何もかもがうまくいく魔法の制度」ではなく、デメリットもあります。
ここでは、人事評価制度のデメリットと注意点を3つ解説します。
導入や運用には手間がかかる
人事評価制度の導入は、規程のテンプレートなどをそのまま流用したり、社労士に「丸投げ」をして完成した規程をそのまま活用したりして実現できるものではありません。
人事評価制度を導入するには自社に合った評価制度を検討したうえで、評価と等級、報酬との関連付けを検討したり、具体的な評価基準や評価手法を1つずつ検討したりする必要があります。
特に、評価基準は自社の目指すべき方向性や望ましい従業員像などから「逆算」をして検討する必要があり、これには相当の手間と時間を要するでしょう。
また、実際に人事評価制度を運用していくにあたっては、評価者の育成やフィードバックなども必要です。
評価者が人事評価制度を正しく理解していないと恣意的な評価がなされ、むしろ不公平感が募ってしまうおそれがあるためです。
人事評価制度の導入にあたってサポートを受ける社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入支援実績が豊富であり、クライアント様の目的に合った制度導入をサポートします。
従業員から反発されるおそれがある
人事評価制度の導入に際しては、従業員から反発される可能性があります。
人事評価制度は従業員の報酬などに直結し得る制度であり、従業員が「報酬を下げるための口実ではないか」「自分の報酬が大きく下がるのではないか」などと不安に感じやすいためです。
従業員の誤解を解くため、企業としては人事評価制度を導入する目的を丁寧に説明する必要があるでしょう。
また、人事評価制度の導入が理由であるからといって、企業側の都合による一方的な減給が許されるわけではありません。
人事評価制度の導入によって大幅な減給となるなど不利益変更に該当する従業員がいる場合は、個々の従業員に丁寧に説明をしたうえで、同意を取り付けるなどの対応が必要となります。
制度導入時に一気に減額をするのではなく、一時的な手当を支給して数年にわたってゆるやかな着地となるよう設計することも1つの方法でしょう。
お困りの際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
評価基準や手法などに問題があればモチベーション低下につながるおそれがある
人事評価制度を導入する主な目的の項目で解説したように、本来、人事評価制度は従業員のモチベーション向上に寄与すべきものです。
しかし、人事評価制度の評価基準や評価手法などに問題があると、公平な評価は実現できません。
むしろ、モチベーションの低下につながるおそれもあるでしょう。
そのような事態を避けるため、人事評価制度の設計は多方面から検証したうえで、慎重に行うことをおすすめします。
人事評価制度の導入にあたってサポートを受ける社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までお問い合わせください。
人事評価制度を導入し目的を達成するポイント
人事評価制度の導入によって期待どおりに目的を達成するためには、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
最後に、人事評価制度を導入して目的を達成するポイントを4つ解説します。
目的を明確にしたうえで導入する
1つ目は、自社が人事評価制度を導入する目的を明確にすることです。
たとえば、自社にとっての課題が「頑張っている人を的確に評価できていない」場合は、頑張っている人を適正に評価することに主軸を置いて制度を設計することになります。
その過程では、自社にとっての「頑張っている人」とはどのような人なのかなど、掘り下げて検討していくことになるでしょう。
同様に、自社にとっての課題が「人材のミスマッチ」にある場合は、各ポストの役割や求められる能力の明確化などに主軸が置かれるはずです。
このように、自社が達成したい目的によって制度設計のポイントは異なります。
そうであるにもかかわらず、導入の目的が明確に定まっていない場合は、目的を達成することはできません。
自社に合った制度設計をする
2つ目は、自社に合った制度設計をすることです。
人事評価制度の導入は、決まったパッケージを導入して実現できるものではありません。
他社の規程を流用したところで、ビジョンや目的、課題、規模、業種、組織体系などがすべて同じ企業など存在せず、テンプレートをそのまま活用すれば齟齬が生じてしまうでしょう。
また、このような付け焼き刃の導入では制度自体に無理が生じ、従業員のモチベーションが低下する可能性も否定できません。
人事評価制度の導入によって目的を達成するには、自社に合った制度設計をする必要があります。
定期的に見直しをする
3つ目は、定期的に見直しをすることです。
人事評価制度は、時の経過とともに実態とのズレが生じる可能性があります。
たとえば、AIの活用を評価基準に入れたい場合であっても、数年前に作成した評価基準にはこれが反映されていない可能性が高いでしょう。
また、このような環境面の変化がなかったとしても、いったん作成した評価基準を実際に運用していく中で、改善点が見つかることは少なくありません。
そのため、作成をした人事評価制度は、実態や時代の流れに応じて定期的に見直す必要があります。
実績豊富な社労士のサポートを受ける
4つ目は、実績豊富な社労士のサポートを受けることです。
自社の目的に合った人事評価制度を的確に導入し運用することは、容易ではありません。
そのため、人事評価制度の導入にあたっては、人事評価制度の導入視線実績が豊富な社労士のサポートを受けることをおすすめします。
社労士のサポートを受けることで自社に合った評価制度の選定が可能となるほか、自社の目的に合わせた制度設計が可能となります。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
まとめ
人事評価制度の概要や導入の目的、導入のデメリットと注意点などについて解説しました。
人事評価制度とは、個々の従業員の能力やスキルを適正に評価し、これを等級アップや報酬などの待遇へと反映させる仕組みです。
人事評価制度を導入する目的としては、企業理念の浸透や待遇の不公平感の解消、従業員のモチベーション向上、適材適所の実現などが挙げられます。
一方で、評価基準などに問題があると、むしろモチベーションの低下につながったり反対意見が出たりする可能性があります。
目的に合った的確な人事評価制度導入を実現するため、導入にあたっては社労士のサポートを受けるとよいでしょう。
Authense社会保険労務士法人は、人事評価制度の導入支援について豊富な実績を有しており、目的に沿った制度の導入をサポートします。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。