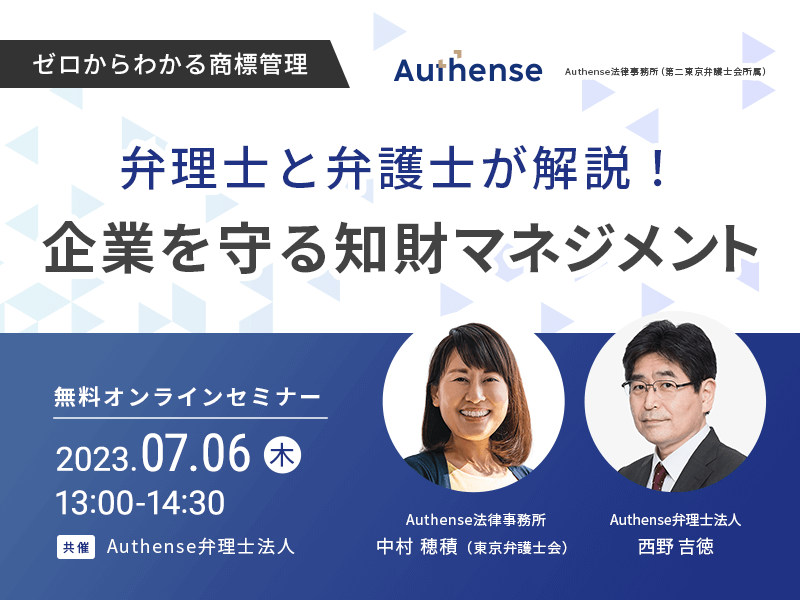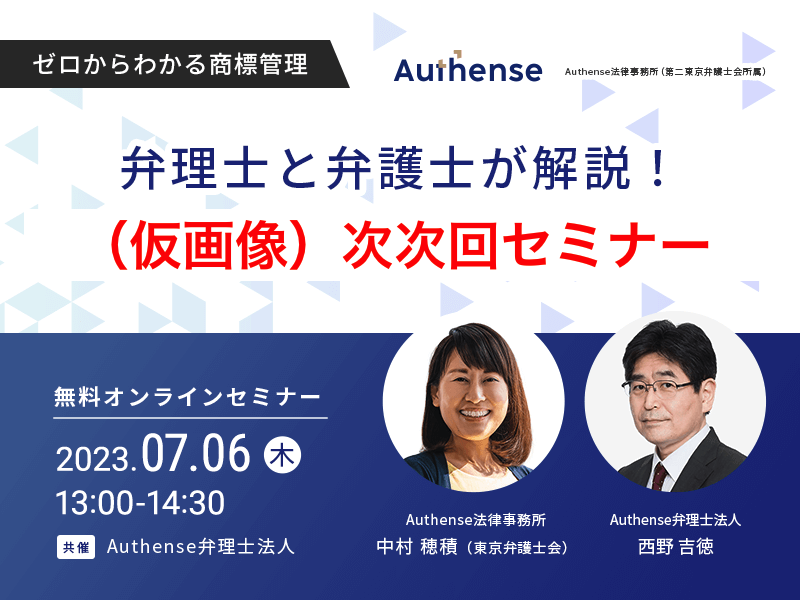人事評価制度は、多くの企業で採用されています。
人事評価制度を導入することで、公正な評価の実現や従業員のモチベーションアップなどにつながるでしょう。
では、人事評価制度は中小企業にも必要なのでしょうか?
また、中小企業が人事評価制度を検討すべきなのは、どのようなタイミングなのでしょうか?
今回は、中小企業が人事評価制度を導入するメリットや導入を成功させるポイント、導入を検討すべきタイミングなどについて社労士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)は人事評価制度の導入支援を行っており、中小企業についても豊富なサポート実績を有しています。
人事評価制度の導入を検討している中小企業は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
目次
人事評価制度は中小企業でも必要?
人事評価制度とは、個々の従業員のスキルや能力を一定の基準で評価し、これを昇進や待遇へと反映させる一連の仕組みです。
従業員数の多い比較的規模の大きな企業で導入されることが多いものの、中小企業にも少なからず導入されています。
特に、今後成長を目指したい場合や新卒採用に踏み切りたい場合などには、中小企業であっても導入を検討するとよいでしょう。
中小企業が人事評価制度を導入する主なメリットは、次でくわしく解説します。
中小企業が人事評価制度を導入する主なメリット
中小企業が人事評価制度を導入するメリットは、小さいものではありません。
ここでは、主なメリットを4つ解説します。
- 経営理念が社内に浸透しやすくなる
- 公平性の高い人事評価が実現でき、従業員が定着しやすくなる
- 従業員のモチベーションが向上しやすくなる
- 適材適所の人材配置が実現しやすくなる
- コミュニケーションが活性化しやすくなる
経営理念が社内に浸透しやすくなる
人事評価制度の評価基準はさまざまであるものの、企業理念に即した行動を評価対象とすることができます。
理念に沿った行動をすることが評価の向上につながるため、従業員に経営理念をより浸透させやすくなります。
公平性の高い人事評価が実現でき、従業員が定着しやすくなる
適切な人事評価制度がない場合には年功序列などで単純に処遇を決めるほかなく、「会社のために頑張っているにもかかわらず、さして頑張っていないように見える同僚と処遇が同じである」などの事態が生じます。
このような事態が横行してしまうと、従業員が不公平に感じ、退職を検討することにもなりかねません。
人事評価制度を導入することで公平な人事評価を実現でき、従業員の定着率向上につながります。
従業員のモチベーションが向上しやすくなる
人事評価制度を導入することで、「何をどれだけ頑張れば、等級が上がるのか」が明確になります。
「頑張った分だけ評価される」仕組みであるうえ、努力すべき方向性も明確となるため、従業員のモチベーションが向上しやすくなります。
適材適所の人材配置が実現しやすくなる
人事評価制度を導入することで、各ポスト(等級)の役割やそのポストに就く人に求められる能力が明確となります。
これと、各従業員が有するスキル・能力を照らし合わせることで、適材適所の人材配置が実現しやすくなります。
コミュニケーションが活性化しやすくなる
人事評価制度にはさまざまな手法があるものの、評価にあたって上司との面談が必要となるものも少なくありません。
たとえば、成果評価の1つであるMBO(Management By Objectives:従業員が自身で目標値を設定し、その達成度で評価する評価手法)では、目標の適正性を確認したり達成度合いを把握したりする過程で、上司との面談をすることとなります。
これにより、これまで以上に上司と部下との理解が深まり、社内のコミュニケーションが活性化しやすくなります。
中小企業が人事評価制度の導入を成功させるポイント
中小企業が人事評価制度の導入を成功させるには、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
ここでは、主なポイントを4つ解説します。
導入の目的を明確にする
1つ目は、人事評価制度を導入する目的を明確にすることです。
人事評価制度は、その導入自体が目的となるものではありません。
たとえば、「従業員が増えて公平な評価が難しくなってきたので、評価の仕組みを整えたい」、「新卒採用へ向けて、評価制度を整えたい」など自社にとっての何らかの課題と目的があり、これを解決するため手段の1つとして人事評価制度があるという位置づけです。
目的があいまいなまま制度を導入してしまうと、思ったような成果が得られず、失敗に終わる可能性があるでしょう。
自社に合った制度を導入する
2つ目は、自社に合った制度を導入することです。
そもそも、人事評価制度の運用には、それなりの手間がかかるものです。
導入さえすれば、自動的に公正な評価が実現できるようなものではありません。
この点を考慮せず、大企業並みの複雑な制度を導入すれば、運用の煩雑さに現場が疲弊するおそれがあるでしょう。
他の企業を真似るのではなく、自社が無理なく運用できる理解しやすい制度設計とすることがポイントです。
導入後もフィードバックをして改善をはかる
3つ目は、導入後もフィードバックをして改善をはかることです。
人事評価制度は普遍的なものではなく、時代の流れや組織の変化などによって実態にそぐわなくなる可能性があります。
そのため、定期的に見直しを行い、改善をする必要があります。
社労士のサポート受ける
4つ目は、社労士のサポートを受けることです。
的確な人事評価制度の導入には専門的な知識や経験が必要であり、中小企業が自社のみで行うことは容易ではありません。
そのため、導入にあたっては、実績豊富な社労士のサポートを受けるとよいでしょう。
中小企業での人事評価制度の導入について相談できる社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までご連絡ください。
中小企業が人事評価制度の導入を検討すべきタイミング
中小企業であっても人事評価制度の導入が有用であるとはいえ、従業員が5人程度の企業で人事評価制度を導入したところで、メリットよりも煩雑さのほうが勝ってしまうでしょう。
また、その後従業員が増えていく中では、大幅な制度変更が必要となります。
そこでここでは、中小企業が人事評価制度の導入を検討すべき具体的なタイミングについて解説します。
自社が人事評価制度を導入するか否か判断に迷っている際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
現状や将来展望などを踏まえ、人事評価制度を導入すべきか否かなど、専門的な知見からアドバイスします。
従業員数が50名程度となったとき
中小企業が人事評価制度の導入を検討すべき1つの目安が、従業員数が50名程度を超えていることです。
この程度の規模になると、トップがすべての従業員の働きぶりをリアルタイムで把握することが困難となるでしょう。
そこで、公平な評価を実現するため、人事評価制度の導入を検討することとなります。
新卒採用を検討するとき
企業を立ち上げた当初は、社長や共同経営者、親族などだけで組織を運営することも少なくありません。
ある程度忙しくなったら、パートタイマーを採用したり、知人の紹介などで即戦力となる従業員を採用したりします。
その後、事業がある程度軌道に乗り始めた段階で、新卒での従業員採用に踏み切ることが多いでしょう。
しかし、新卒採用を成功させるには、社内でのキャリアパスや評価制度がある程度明確になっている必要があります。
そこで、新卒採用を検討する段階で、人事評価制度の導入を検討することとなります。
さらなる成長を目指すことを決めたとき
現状として従業員数が50人に満たなくても、すでに企業のビジョンが明確であり、かつさらなる拡大を目指したいと検討している場合は、人事評価制度の導入を検討するとよいでしょう。
早い段階から人事評価制度を導入することで、運用をしながら時間をかけて評価者を育成したり、制度をブラッシュアップしたりすることが可能となります。
また、社内の評価制度が整っていることで安心感が生まれ、人材採用においても有利となる効果が期待できます。
人事評価制度を中小企業が導入する基本ステップ
中小企業が人事評価制度を導入する場合、どのようなステップで進めればよいのでしょうか?
ここでは、人事評価制度を導入する基本のステップについて解説します。
- 社労士へ相談する
- 人事に課する課題を洗い出し人事評価制度導入の目的を定める
- 人事評価制度を選定する
- 人事評価の基準・手法を決める
- 社内に周知し運用を開始する
- 定期的に見直す
社労士へ相談する
中小企業が自社に合った的確な人事評価制度を導入するには、社労士のサポートを受けるのが近道です。
そのため、人事評価制度の導入を検討している段階で、まずは社労士に相談をするとよいでしょう。
導入を迷っている段階であっても、社労士に相談することで、人事評価制度の導入が自社にとってプラスとなりそうか否かの見通しを立てることが可能となります。
人事評価制度の導入について相談できる実績豊富な社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人へお問い合わせください。
人事に課する課題を洗い出し人事評価制度導入の目的を定める
社労士とともに、人事に関する自社の課題を洗い出し、人事評価制度の導入目的を定めます。
先ほど解説したように、人事評価制度の導入はそれ自体が目的となるものではありません。
自社にとっての課題や導入の目的を明確にすることで、その課題解決に資する人事評価制度の設計が実現できます。
人事評価制度を選定する
人事評価制度には、さまざまな種類が存在します。
代表的なものは、次のとおりです。
- 成果評価:売上高や生産量など、従業員の業務上の成果を評価するもの
- 能力評価:業務上遂行の能力やスキル、素質を評価するもの
- 行動評価:経営理念に沿った行動を評価するもの
- 360度評価:上司のほか、部下や同僚など複数の関係者が評価するもの
これらの評価制度には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、「どれがよい」と一律にいえるものではありません。
そのため、自社の状況や将来展望に合わせて最適な手法を検討することとなります。
人事評価の基準・手法を決める
評価の枠組みを選定したら、人事評価の基準と手法を定めます。
たとえば、「能力評価」を採用する場合、具体的にどのような能力やスキルを評価対象とするのか、そしてその能力やスキルをどのように評価するのかなど、詳細を詰めるということです。
「コミュニケーション力」を評価対象とする場合、これだけでは曖昧であり適切な評価が困難です。
そこで、企業が求めるスキルからこれを細分化し、たとえば「業務に行き詰った際に、期日に余裕をもって上司へ相談できる」、「顧客と直接対話をし、課題解決の方向性を決めることができる」など具体化します。
評価基準を明確にすることで、評価者の主観によるブレを避けやすくなり、評価の公平性を担保しやすくなります。
社内に周知し運用を開始する
人事評価制度がある程度構築できた段階で、社内へ周知し、運用を開始します。
なお、突如として「人事評価制度を導入する」とだけ告げてしまうと、社内で混乱が生じかねません。
従業員が制度内容をよく理解できず、「自身の給与が下がるのではないか」などと不安に感じる可能性があるためです。
そのような事態を避けるため、人事評価制度の導入にあたっては、導入の目的などを丁寧に説明する必要があります。
併せて、適正な評価を実現するため、評価者の教育も必要になります。
定期的に見直す
時代の経過や企業の成長とともに、評価基準が現状にそぐわなくなる可能性があります。
また、どれだけ慎重に検討した制度であっても、導入後に課題や改善点が見つかることもあるでしょう。
そのため、人事評価制度は導入後も定期的に見直しをする必要があります。
中小企業が人事評価制度を導入する際の注意点
中小企業が人事評価制度を導入することには、注意すべき点もあります。
最後に、人事評価制度を中小企業が導入する際の注意点を2つ解説します。
導入や運用には手間がかかる
1つ目は、人事評価制度の導入や運用には手間がかかることです。
先ほど「導入のステップ」でも解説したように、人事評価制度は所定のパッケージを採用したり社労士に「丸投げ」をしたりしてすぐに導入できるものではありません。
自社に合った評価制度を選択し、評価基準や評価手法などを定めるステップが必要です。
また、「導入さえすれば自動的に人事評価がうまくいく」わけでもありません。
導入にあたっては適正な評価が実現されるよう評価者を教育する必要があるほか、評価基準や評価手法に問題がないか定期的にフィードバックをする必要があります。
しかし、これらの手間は、社労士のサポートを受けることで大きく軽減できます。
人事評価制度の導入にあたってサポートを受ける社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
評価手法や評価基準に納得感が得られなければモチベーション低下につながるおそれがある
2つ目は、評価手法や評価基準に納得感が得られなければ、モチベーション低下につながるおそれがあることです。
本来、人事評価制度は従業員のモチベーション向上に寄与すべき制度であるはずです。
しかし、評価手法に問題があり評価者の主観だけで評価がなされる状態となっていたり、評価基準に問題があり業績向上につながる貢献が適正に評価されない事態となっていたりしてしまうと、むしろモチベーションの低下につながるかもしれません。
中小企業で従業員の士気が低下してしまえば、会社の死活問題につながりかねないでしょう。
そのような事態を避けるため、中小企業が人事評価制度を導入するにあたっては、評価手法や評価基準などに問題がないか慎重に検討する必要があります。
社労士のサポートを受けることで、自社に合った的確な人事評価制度を設計しやすくなります。
人事評価制度について中小企業への導入支援実績が豊富な社労士をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
まとめ
人事評価制度を中小企業が導入するメリットや導入を成功させるポイント、中小企業が人事評価制度を導入するステップなどを解説しました。
中小企業であっても、従業員数が50人程度となったときやさらなる成長を目指したいときなどには、人事評価制度の導入を検討するとよいでしょう。
中小企業が人事評価制度を導入することは、従業員のモチベーション向上や定着率の向上、公平な人事評価などにつながり、メリットが小さくありません。
しかし、人事評価制度の設計に問題があれば、導入の意図に反してモチベーションの低下につながるおそれがあります。
そのような事態を避けるため、中小企業が人事評価制度を導入するにあたっては、社労士のサポートを受けるのがおすすめです。
実績豊富な社労士のサポートを受けることで、自社に合った的確な人事評価制度の導入が実現でき、制度導入によるメリットを享受しやすくなるためです。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入支援に力を入れており、中小企業ついても多くのサポート実績を有しています。
中小企業で人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。