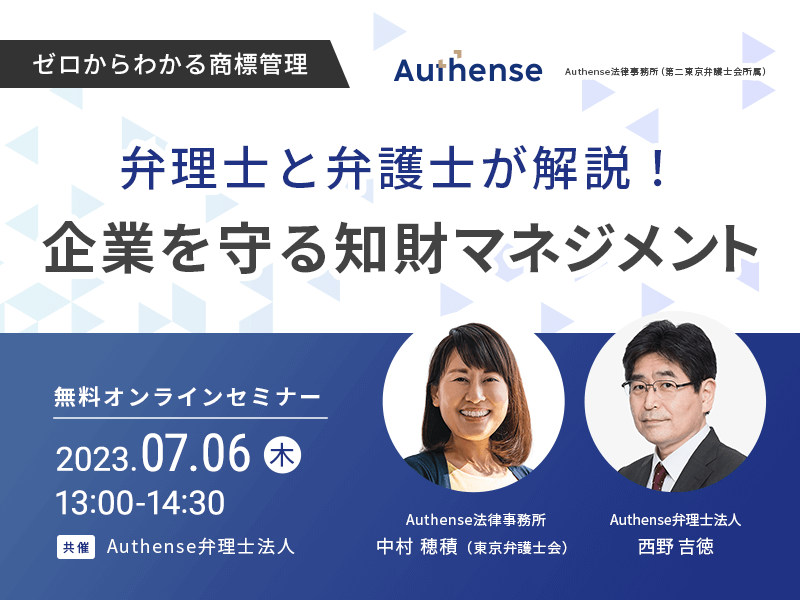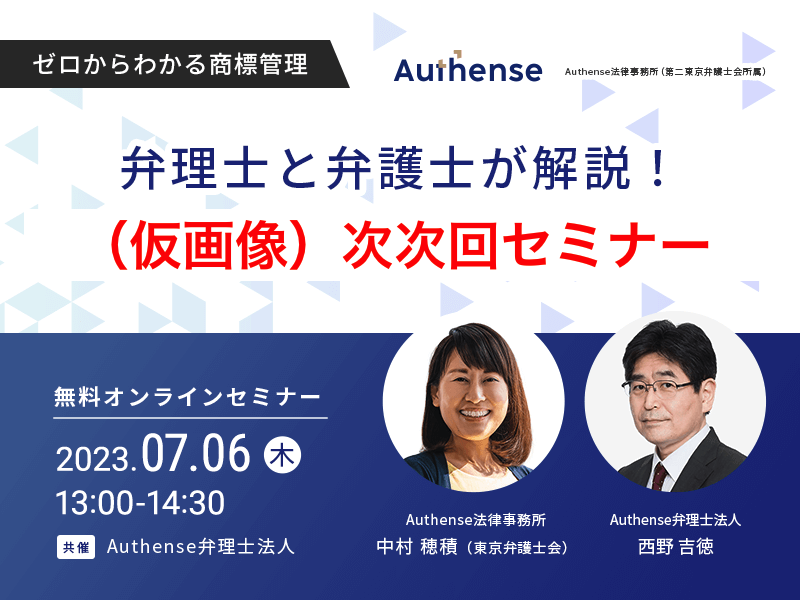適切な「人事評価制度」を導入することで、従業員のモチベーションが向上し、さらなる業績向上や従業員の定着につながる効果を期待できます。
では、人事評価制度とはどのようなものなのでしょうか?
また、人事評価制度の導入には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
今回は、人事評価制度の概要や導入の目的、メリット・デメリット、人事評価制度の作り方などについて社会保険労務士(社労士)がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)は人事評価制度の作成支援について豊富な実績を有しており、クライアント様のご希望に合った人事評価制度の作成・導入をサポートします。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
人事評価制度とは
人事評価制度とは、従業員の職務遂行能力や業績などを定量的・定性的に評価し、これを報酬や待遇などに反映させる仕組みを指します。
「人事評価制度の導入」は1つの規程だけを新たに作成して完結するものではなく、必要に応じて新たな規程を作成したり、既存の規程を改訂したりして導入するものです。
従業員への影響も小さくないため、導入にあたっては人事評価制度を導入する目的をしっかりと見定めたうえで、自社に及ぶ影響を慎重に検討する必要があるでしょう。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までまずはお気軽にご相談ください。
人事評価制度の主な目的・意義
人事評価制度は、どのような目的で導入するものなのでしょうか?
ここでは、人事評価制度の主な目的と意義を5つ解説します。
自社が目指す方向や自社が求める社員像を明確にすること
1つ目は、自社が目指す方向や、自社が求める社員像を明確にすることです。
自社の目指すべき方向性と求める人物像がズレていたり、求める人物像がそもそも明確となっていなかったりする企業は少なくありません。
人事評価制度を導入し、自社の目指すべき方向性から「逆算」をして自社が求める人物像を明確とすることで、人材とのミスマッチが起きづらくなります。
人材の適正配置を実現すること
2つ目は、人材の適正配置を実現することです。
ポストや役職ごとに求める人材が明確となっていないと貴重なリソースである人材を適正に配置することは困難であり、非効率となりかねません。
人事評価制度を導入してポストごとに求める能力や熟練度、役割などを明確にすることで、人材の適正配置を実現しやすくなります。
生産性を向上させること
3つ目は、生産性を向上させることです。
人事評価制度がない企業では、ポストごとの役割が明確になっていないことが多いでしょう。
そのため、ポストが乱立していたり、複数の部署で重複する業務を行っていたりするなどの非効率が生じやすくなります。
人事評価制度を導入してポストごとの役割を整理することで、会社全体の生産性が向上する効果を期待できます。
評価項目や基準の明確化により、人材育成につなげること
4つ目は、評価項目の基準の明確化によって、人材育成につなげることです。
どのような基準を満たすと昇進できるのかが明確となっていなければ、従業員が努力の方向を間違えることとなりかねません。
人事評価制度を導入することで「何をすれば昇進できるのか」「どのような基準を満たせば希望するポストに異動できるのか」が明確となり、効率的な人材育成が可能となります。
待遇差による不満を減らすこと
5つ目は、待遇の差による不満を減らすことです。
人事評価の基準が不明瞭である場合、「自分の方が頑張っているのに、なぜあの人の方が評価が高いのか」などの不満が生じかねません。
また、このように部下から問われた際に、明確に理由を説明しづらい場合もあるでしょう。
待遇差による不満が募ると、モチベーションが低下するおそれも生じます。
人事評価制度を導入して評価基準が明確となることで、不明瞭な待遇差による不満を解消しやすくなります。
人事評価制度の主な構成要素
人事評価制度は、主に次の3つで構成されます。
- 等級制度
- 評価制度
- 報酬制度
ここでは、それぞれの構成要素の概要を解説します。
等級制度
等級制度とは、従業員の業務遂行能力や熟練度などに応じた等級を決定する制度です。
等級制度には、主に次の3つが存在します。
- 職能資格制度:職務遂行能力によって等級が区分され、経験により等級が上がる制度。原則として降格がない。
- 職務等級制度(成果主義):担当する職務の内容・難易度によって等級が区分され、要求内容を達成できる状態となることで等級が上がる制度。
- 役割等級制度(ミッショングレード制):与えられた役割と遂行能力によって等級が区分され、達成度合いにより等級が変動する制度。
等級制度は人事評価の内部資料として作成するのではなく、個々の従業員が「何を達成すれば等級が上がるのか」を認識できる状態とすることがポイントです。
社労士へ相談したうえで、自社に合った等級制度を導入しましょう。
評価制度
評価制度とは、一定の指標を基準として、従業員の能力や会社への貢献度などを評価する制度です。
評価制度には、次のものなどさまざまな種類が存在します。
- MBO(目標管理制度):企業の方針と個々の従業員の目標を調整して個々の従業員が達成すべき具体的な目標を設定し、その達成度合いで評価する手法
- 360度評価:評価対象者の上司や同僚、部下など立場の異なる複数の人物が評価する手法
- OKR:企業・部署・個人間で連携した目標の達成度合いに応じて評価する手法
従業員を適切に評価する仕組みがないと、従業員の等級を的確に判定することができません。
そのため、先ほど紹介した等級制度とこの評価制度は、両輪であるといえます。
報酬制度
報酬制度とは、給与や賞与の額を定める制度です。
人事評価制度を導入する場合、従業員の等級や評価と報酬とを紐づけることとなります。
人事評価制度のメリット
人事評価制度の導入には、企業にとって多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを6つ解説します。
ただし、これらのメリットを享受するには、自社に合った的確な人事評価制度であることが大前提となります。
人事評価制度に関する相談先をお探しの際は、Authense社会保険労務士法人までお問い合わせください。
企業理念やビジョンが浸透しやすくなる
1つ目は、企業理念やビジョンが浸透しやすくなることです。
人事評価制度を導入する際は、まず企業理念やビジョンを明確化したうえで、これに寄与する人材を評価する仕組みを構築することとなります。
反対に、企業理念やビジョンに反する取り組みは、いくら努力したところで評価されません。
評価が上がるか否かが企業理念やビジョンの達成に寄与するか否かによって左右されることになるため、個々の従業員が企業理念やビジョンを意識しやすくなります。
人材の育成計画が立てやすくなる
2つ目は、人材の育成計画が立てやすくなることです。
人事評価制度を導入することで、何を達成することで従業員の等級が上がるのかが明確になります。
そのため、個々の従業員の達成度合を確認して現状として等級の引き上げに不足している部分を強化するなど、人材の育成計画が立てやすくなります。
従業員のモチベーション向上につながる
3つ目は、従業員のモチベーション向上につながることです。
不明瞭な人事評価がなされていないと「何をすれば評価が上がるのか」がわからず、モチベーションが低下してしまいかねません。
人事評価制度を導入することで、等級を上げるために尽力すべきことが明確となるため、モチベーションの向上につながりやすくなります。
生産性向上につながる
4つ目は、生産性の向上につながることです。
先ほど解説したように、人事評価制度を導入することで会社が目指すべきビジョンが明確となります。
また、各ポストが担うべき役割なども整理され、業務の重複などの非効率も生じづらくなります。
これにより、生産性が向上する効果が期待できます。
人事評価の労力が軽減される
5つ目は、人事評価の労力が軽減されることです。
人事評価制度がない場合、人事評価にあたっては個々の従業員の活躍や寄与を個別に評価するほかなく、多大な労力を要します。
人事評価制度を導入することで、評価にあたって確認すべき点や基準が明確となり、人事評価の労力削減が可能となります。
公平な人事評価が実現しやすくなる
6つ目は、公平な人事評価が実現しやすくなることです。
人事評価制度がない場合、人事評価にあたって評価者の裁量が強くなります。
その結果、評価者の主観やアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)の影響を受けやすくなり、人事評価が不公平なものとなりかねません。
不公平な評価が横行すると、モチベーションが低下したり、評価者に好感を持ってもらうために従業員が企業の業績向上とは無関係な努力をしたりするなどの非効率が生じるおそれもあるでしょう。
人事評価制度を導入することで、評価者の主観に左右されづらい画一的な評価が可能となり、公平な人事評価を実現しやすくなります。
人事評価制度のデメリット・課題
人事評価制度の導入には、デメリットや課題も存在します。
そのため、導入にあたってはデメリットも理解したうえで、人事評価制度の導入が自社にとってプラスとなるのか慎重に検討することをおすすめします。
ここでは、人事評価制度の代表的なデメリットと課題を3つ解説します。
人事評価制度を導入するか判断に迷う際には、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
導入に手間と労力がかかる
人事評価制度を導入するには、相当の手間と労力がかかります。
人事評価制度は他社の制度をそのまま流用できるようなものではなく、自社のビジョンや業務内容に応じて設計する必要があるためです。
また、社労士は最大限のサポートを行うものの、社労士に「丸投げ」をして完成するようなものでもありません。
自社の人事制度を抜本的に変える制度であることを理解したうえで、労力をかける覚悟をもって準備に取り掛かる必要があるでしょう。
評価者の育成が必要となる
人事評価制度を的確に運用するには、評価者の教育や育成が必要となります。
制度を導入しても、実際に評価をする者がこれを十分に使いこなせなければ、制度が形骸化しかねないためです。
モチベーションの低下につながる場合がある
人事評価制度を導入する最大の懸念事項は、経営陣の期待に反し、従業員のモチベーションが低下するおそれがあることです。
人事評価制度は評価基準が明確であり、ある程度画一的に評価がされます。
そのため、端的に表現すると、従業員が「評価につながらない仕事をしない」方向に舵をきるおそれも否定できません。
しかし、これは人事評価制度自体のデメリットではなく、評価項目の設定を誤った場合に生じ得るリスクです。
企業に貢献している従業員の努力を切り捨ててモチベーションを低下させることのないよう、人事評価制度を導入する際は、評価項目を慎重に検討する必要があります。
人事評価制度を導入する流れ
人事評価制度は、どのような流れで導入すればよいのでしょうか?
ここでは、人事評価制度の作り方と導入の流れを解説します。
人事評価制度にくわしい社労士に相談する
人事評価制度の導入にあたっては、自社の規程を抜本的に改訂すべき場合も多く、容易なことではありません。
そのため、まずは人事評価制度にくわしい社労士に相談したうえで、人事評価制度を導入するか否かの段階から慎重に検討することをおすすめします。
人事評価制度について相談できる社労士をお探しの際は、当事務所(Authense社会保険労務士法人)へご相談ください。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入支援実績が豊富であり、導入する制度の検討から導入後の運用に至るまで、総合的なサポートが可能です。
自社の現状を把握する
自社の現状を把握し、課題を明確にします。
このステップでは、従業員からも意見を聴取するとよいでしょう。
現状の人事制度に対する従業員の不満や不安を知ることで、人事評価制度の導入目的を明確化しやすくなるためです。
特に、人事評価に対する不公平感が強い場合や会社の求める従業員像がわからず不安を感じている場合、これによりモチベーションが低下している場合などには、適切な人事評価制度の導入によって不満を解消できる可能性が高いといえます。
評価基準や項目を策定する
次に、人事評価制度の中心となる、具体的な評価基準や評価項目を策定します。
ここでは、自社が求める従業員像を検討したうえで、能力や勤務態度、成果、行動など、これを評価する具体的な指標を検討します。
評価基準や評価項目は、必ずしもすべての職種で統一する必要はありません。
たとえば、営業職と研究職とでは求められる能力や人物像が異なることはもちろん、成果が出るスパンなども異なるためです。
このステップが人事評価制度の導入における中核となるため、社労士のサポートを受けたうえで入念に検討する必要があるでしょう。
評価方法を決定する
次に、評価方法を決定します。
ここでは、具体的な評価方法や個々の評価する段階の数(3段階評価なのか、5段階評価なのかなど)のほか、評価の結果と処遇との対応などを検討します。
また、複数の評価項目がある場合には、どの項目にどの程度のウエイトを置くのかなどについても併せて検討しなければなりません。
評価方法は評価者の主観によって評価に大きなズレが生じにくいことに重点を置くとよいでしょう。
一方で、評価があまりに煩雑であり形骸化しては本末転倒であるため、無理なく運用できることもポイントです。
導入スケジュールを作成する
続いて、具体的な導入スケジュールを検討します。
導入スケジュールは決算期に合わせることが多いものの、準備不足から混乱が生じることのないよう、無理のないスケジュールを組むことをおすすめします。
従業員に説明をする
人事評価制度の案が固まった段階で、従業員に対して説明会を実施します。
説明会では人事評価制度の概要や導入の目的、導入時期のほか、具体的な評価基準や評価者など、齟齬が生じないよう丁寧に説明しましょう。
新たな制度の導入によって「自身の給与が下がる」などと不安に感じる従業員が多いと、モチベーションの低下につながるかもしれません。
そのような事態を避けるため、公正な人事評価を実現する目的であることなどを丁寧に説明することが求められます。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の作成のみならず、従業員に説明すべきポイントなどについてもアドバイスを行っています。
人事評価制度導入に関するトータルサポートをご希望の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
人事評価制度の導入を成功させるポイント
人事評価制度の導入を成功させるには、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
最後に、人事評価制度の導入を成功させるポイントを2つ解説します。
実績豊富な社労士のサポートを受ける
1つ目は、実績豊富な社労士のサポートを受けることです。
繰り返し解説したように、適切な人事評価制度を自社だけで行うのは容易なことではありません。
また、人事評価制度の導入に失敗すれば多くの従業員が退職するなど、取り返しのつきにくい影響が及ぶおそれもあります。
そのような事態を避けるため、人事評価制度の導入は実績豊富な社労士のサポートのもと、慎重に進めることをおすすめします。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入サポートについて豊富な実績を有しており、クライアント様の実情や将来展望に即した制度設計を支援します。
人事評価制度の導入をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
トレンドに流されず自社の目的に合った人事評価制度を検討する
2つ目は、トレンドに流されず、自社に合った人事評価制度を検討することです。
人事評価制度の導入は、それ自体が目的となるものではありません。
自社に何らかの課題が存在し、その課題を解決する手段の1つとして導入を検討すべきものです。
確かに人事制度には一定のトレンドがあり、「人事評価制度を導入するとよい」「成果主義がよい」「ジョブ型がよい」など、さまざまな声が聞こえてくるかもしれません。
しかし、人事制度は流行り廃りに応じて簡単に変更すべきものではなく、自社の将来展望を見据え、これを実現するために適した制度を慎重に選定すべきものです。
「流行りであるから」といった理由で安易に制度を導入し従業員の処遇を変更すれば、翻弄されることに疲れた従業員のモチベーションが低下し、退職されてしまうおそれもあるでしょう。
トレンドに流されるのではなく、自社のさらなる成長を見据え、自社に合った制度の導入を慎重に検討することが導入成功のポイントであるといえます。
まとめ
人事評価制度の概要や導入の目的、人事評価制度を導入するメリット・デメリットなどを解説しました。
人事評価制度とは、従業員の職務遂行能力や業績などを定量的・定性的に評価し、これを報酬や待遇などに反映させる仕組み全体を指します。
的確な人事評価制度を導入することで公平な人事評価が可能となり、従業員のモチベーションアップや生産性向上などにつながるでしょう。
しかし、評価項目の設定を誤ると、反対に従業員のモチベーションを低下させるおそれも生じます。
また、「トレンドであるから」といって安易に導入することは避け、自社に合っているか否かを慎重に検討したうえで導入すべき制度です。
的確な人事評価制度の導入を自社だけで行うことは容易ではないため、制度に関心がある際は社労士へ相談したうえで、二人三脚で制度設計を進めることをおすすめします。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入支援について豊富な実績を有しており、安心してご相談いただけます。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。