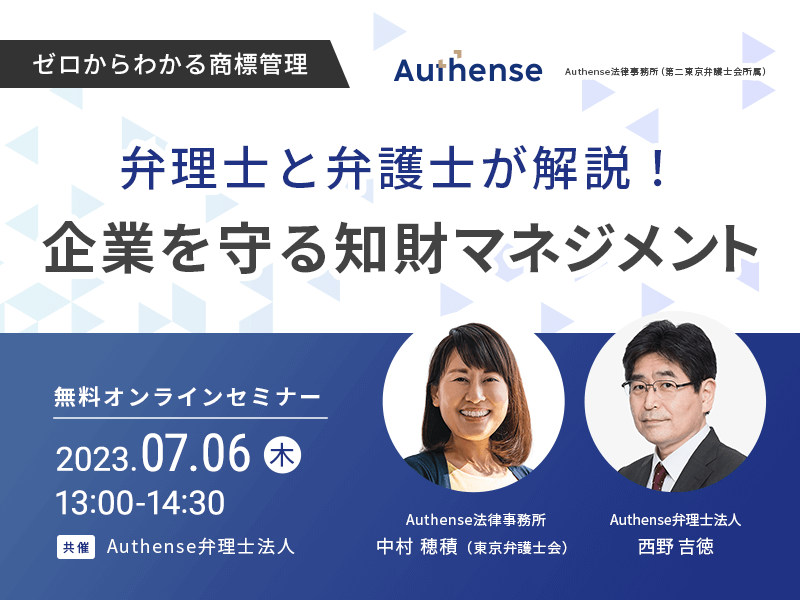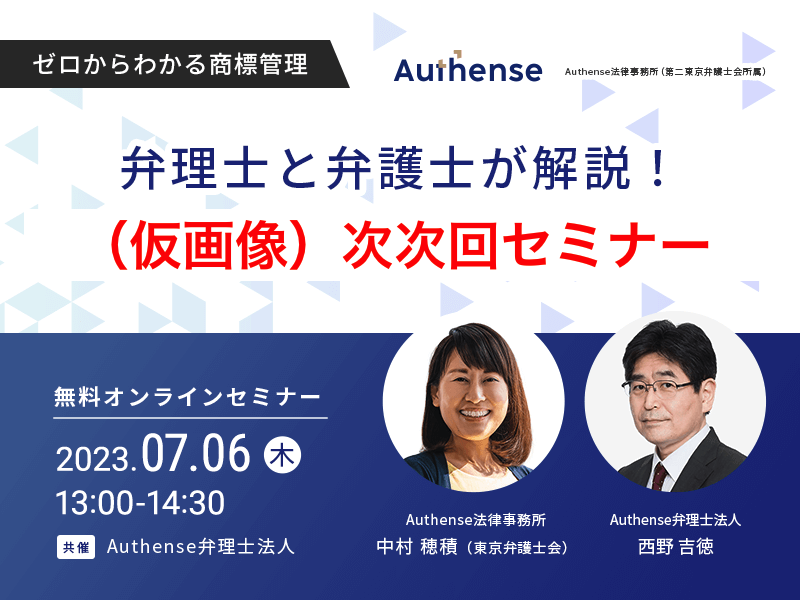えるぼし認定を受けることで、取引先や求職者などに女性の活躍を推進している企業であることがアピールできます。
ほかにも、公共調達や補助金で加点対象となる場合があるなど、メリットは小さくありません。
そもそも、えるぼし認定とはどのような制度なのでしょうか?
また、えるぼし認定を受けるには、どのような基準を満たす必要があるのでしょうか?
今回は、えるぼし認定の概要や認定基準、えるぼし認定に申請する流れなどについて、社会保険労務士(社労士)がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)は、えるぼし認定申請のサポートに関して豊富な実績を有しています。
自社がえるぼし認定基準を満たしているかなど、えるぼし認定について知りたい際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
目次
えるぼし認定制度の概要
えるぼし認定制度とは、女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定を受けるには、行動計画の策定と届出をしたうえで、認定を受けるための申請をしなければなりません。
えるぼし認定には、通常の「えるぼし認定」と、さらに厳しい基準をクリアした企業を対象とする「プラチナえるぼし認定」があります。
ここでは、それぞれの概要について解説します。
えるぼし認定制度とは
はじめからプラチナえるぼし認定を受けることはできず、これからえるぼし認定を申請する企業は、まずはえるぼし認定を目指すこととなります。
えるぼし認定は、1段階目から3段階目までが存在します。
どの段階の認定が受けられるかは、後ほど紹介する5つの「えるぼし認定を受ける基準」を満たした数に応じて、次のように決まります。
| えるぼし認定の段階 | 基準を満たす数 |
| 1段階目(1つ星) | 1つまたは2つ |
| 2段階目(2つ星) | 3つまたは4つ |
| 3段階名(3つ星) | 5つすべて |
つまり、認定を受ける段階にこだわりがない場合は、必ずしも5つの認定要件のすべてを満たす必要はないということです。
ただし、1段階目のえるぼし認定を受けるということは、裏を返すと、5つの要件のうち「3つまたは4つは満たせていない」ことを世間に公表することを意味します。
もちろん、あえて公表することで、ステークホルダーからの適切な監視のもと、さらなるステップアップを目指すモチベーションとすることも1つでしょう。
一方で、「1段階目での取得では意味がないため、3段階目の基準を満たすまで申請しない」というのも1つの考え方です。
自社が認定を目指す段階を検討したい際には、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
プラチナえるぼし認定とは
プラチナえるぼし認定とは、通常のえるぼし認定よりもさらに厳しい基準をクリアした企業に与えられる認定です。
プラチナえるぼし認定を受けるには、すでにえるぼし認定を受けている必要があるため、はじめからプラチナえるぼし認定を目指すことはできません。
これからえるぼし認定を目指す場合は、まずは通常のえるぼし認定を受けて、そのうえでプラチナえるぼし認定へのステップアップを検討するとよいでしょう。
えるぼし認定を受ける基準(女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準)
えるぼし認定には、5つの基準が設けられています。
これらの基準を1つも満たさない場合は認定を受けられないものの、1つでも満たせば1段階目の認定を受けることができ、すべて満たした場合には3段階目のえるぼし認定の対象となります。
ここでは、5つの認定基準の概要を解説します。
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
採用
1つ目の基準は、採用です。
この基準を満たすには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が、同程度であること
- 直近の事業年度において、原則として次の両⽅に該当すること
- 正社員に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
- 正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
継続就業
2つ目の基準は、継続就業です。
この基準を満たすためには、直近の事業年度において、次のいずれかに該当する必要があります。
- 「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が、雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
- 「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が、雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること(新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
ただし、これらを算出できない場合は、次を満たすことでもよいこととされています。
- 直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること
労働時間等の働き方
3つ目の基準は、労働時間等の働き方です。
ここでは、雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休⽇労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとにすべて45時間未満であることが認定基準とされます。
ただし、これによることが難しい場合には、次の式を満たすことでもよいこととされています。
- [「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の⽇数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45時間
管理職比率
4つ目の基準は、管理職比率です。
次のいずれかに該当することで、この基準をクリアすることができます。
- 直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
- 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」が、8割以上であること
多様なキャリアコース
5つ目の基準は、多様なキャリアコースです。
直近の3事業年度のうち、次の4つについて一定数以上の項目を満たす場合に、この基準をクリアできます。
- ⼥性の非正社員から正社員への転換(派遣の場合は、雇入れ)
- ⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- 過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用
- おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用
満たすべき項目の数は、それぞれ次のとおりです。
- 常時雇用する労働者数が301⼈以上の事業主:2項目以上(非正社員がいる場合は必ず1を含むこと)
- 常時雇用する労働者数が300⼈以下の事業主:1項目以上
えるぼし認定を受けるために満たすべきその他の基準
えるぼし認定を受けるには、先ほど解説した5つの基準のほか、ここで解説する3つの要件も満たさなければなりません。
これらは認定を受ける段階に関わらず、必ず満たすべき基準です。
ここでは、それぞれの概要について解説します。
- 事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと
- 策定した一般事業主行動計画について、適切に労働者への周知と外部公表をしたこと
- 一定の欠格要件に該当しないこと
事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと
えるぼし認定を受けるには、事業主行動計画策定指針に即し、適切な一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画)を定めなければなりません。
これは、えるぼし認定の根拠法でもある「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」といいます)」の要請によるものです。
この法律の規定により、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業者は一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出なければなりません(女性活躍推進法8条1項)。
一方で、常時雇用する従業員が100人以下の事業者は、一般事業主行動計画の策定や届出は任意ではなく努力義務とされています(同7項)。
ただし、えるぼし認定を受けたい場合は、従業員数に関わらず、一般事業主行動計画の策定と届出が必要です(同9条)。
策定した一般事業主行動計画について、適切に労働者への周知と外部公表をしたこと
一般事業主行動計画を策定したら、これを労働者に周知するとともに、ホームページに掲載するなどして外部に公表することが求められます。
従業員への周知は、事業所の見やすい場所へ掲示したり、書面を労働者へ交付したり、電子メールで送信したりすることによって行います。
一定の欠格要件に該当しないこと
欠格要件に1つでも該当する場合には、他の要件を満たしていてもえるぼし認定を受けることができません。
主な欠格要件は次のとおりです。
- 認定取消または辞退の⽇から3年を経過していないこと
- 職業安定法の規定により、公共職業安定所等が求⼈の申込みを受理しないことができる場合に該当すること
- ⼥性活躍推進法や⼥性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重⼤事実があること(関係法令に違反する重⼤事実があった事業主は、是正等を確認してから1年間を経過していないこと)
プラチナえるぼし認定を受ける基準
プラチナえるぼし認定を受けるには、通常のえるぼし認定よりも厳しい認定基準をクリアしなければなりません。
ここでは、プラチナえるぼし認定の代表的な基準の概要について解説します。
えるぼし認定企業であること
1つ目の基準は、すでにえるぼし認定企業であることです。
そのため、はじめからプラチナえるぼし認定を受けることはできません。
策定した一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと
2つ目の基準は、策定した⼀般事業主⾏動計画に基づく取組を実施して、その⾏動計画に定めた目標を達成することです。
単に行動計画を定めるのみならず、これを達成することが求められます。
5つの認定基準をすべて満たすこと
3つ目の基準は、5つの認定基準をすべて満たすことです。
5つの認定基準は原則として先ほど紹介した「えるぼし認定」の基準と同じであるものの、「継続就業」や「管理職⽐率」では基準がより厳しいものへと引き上げられています。
男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者を選任すること
4つ目の基準は、次の者を選任することです。
- 男⼥雇用機会均等推進者
- 職業家庭両⽴推進者
一定事項を「女性の活躍推進企業データベース」で公表すること
5つ目の基準は、⼥性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち、8項目以上を「⼥性の活躍推進企業データベース」で公表することです。
公表すべき項目は、「採用した労働者に占める女性労働者の割合」や「男女の賃金の差異」、「男女の平均継続勤務年数の差異」などの中から選択します。
えるぼし認定を申請する流れ
えるぼし認定申請は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
最後に、えるぼし認定の申請をする一般的な流れについて解説します。
えるぼし認定支援の実績が豊富な社労士に相談する
えるぼし認定申請を検討している場合は、まずは社労士へご相談ください。
相談先の社労士は、えるぼし認定申請の実績が豊富であることを基準に選ぶとよいでしょう。
社労士であっても、えるぼし認定申請などに力を入れているかどうかは、事務所によって異なるためです。
Authense社会保険労務士法人は、えるぼし認定申請について豊富な実績を有しており、安心してご相談いただけます。
えるぼし認定申請をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
えるぼし認定の基準を満たしているか確認する
社労士へ相談したら、社労士とともにえるぼし認定の基準を満たしているか確認します。
なお、先ほど解説したように、5つの基準のうち1つでも満たすことができれば、えるぼし認定を受けることは可能です。
しかし、自社が「えるぼし認定を受けるのであれば、3段階目でなければ意味がない」などこだわりがある場合は、希望する認定の要件を満たすか確認するとよいでしょう。
認定基準を満たしている場合:次のステップへ進む
自社がえるぼし認定の基準を満たせそうな場合には、次のステップへと進みます。
認定基準を満たしていない場合:社労士の支援を受けて課題解決を目指す
現状ではえるぼし認定の認定基準をクリアすることが難しい場合、解決すべき課題を定め、将来の認定申請を目指します。
この課題の選定や具体的な解決方法の検討についても、社労士のサポートを受けるとよいでしょう。
⼀般事業主⾏動計画を策定し届け出る
えるぼし認定申請へ進む場合、まずは⾃社の⼥性の活躍に関する状況の把握と課題分析を行います。
そのうえで、自社の課題解決に資する⼀般事業主⾏動計画を策定しましょう。
一般事業主行動計画を策定したら、策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。
なお、一般事業主行動計画の策定と届出は、女性活躍推進法で義務付けられています(女性活躍推進法8条1項)。
常時雇用する従業員数が100人以下の場合には、義務ではなく努力義務であるものの、えるぼし認定申請をする場合には従業員数に関わらず策定と届出をしなければなりません(同7項、9条)。
⼥性の活躍に関する情報を公表する
続いて、⾃社の⼥性の活躍に関する状況について「⼥性の活躍推進企業データベース」や⾃社のホームページなどで公表します。
えるぼし認定申請をする
ここまでのステップが完了したら、えるぼし認定を申請します。
認定基準を満たした項目の数に応じて、第1段階から第3段階のえるぼし認定がなされます。
なお、先ほど解説したように、プラチナえるぼし認定を受けるにはすでに「えるぼし認定」を受けている必要があり、はじめからプラチナえるぼし認定に申請することはできません。
プラチナえるぼし認定を目指す場合は、まず通常のえるぼし認定を受けたうえでステップアップを目指しましょう。
まとめ
えるぼし認定の基準について解説しました。
えるぼし認定は、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定受けると認定内容に応じたマークの使用が可能となるため、顧客や取引先、求職者などに対して自社の女性の活躍を推進している企業であることがアピールしやすくなります。
えるぼし認定には、原則として5つの基準が定められており、基準を満たす数に応じて第1段階から第3段階までのいずれかの認定が受けられます。
さらにステップアップをしたい場合には、既にえるぼし認定を受けている企業のみが対象となる「プラチナえるぼし認定」を目指すとよいでしょう。
Authense社会保険労務士法人は、えるぼし認定の申請サポートに力を入れており、豊富な実績を有しています。
えるぼし認定申請をご検討の際や、自社が認定基準を満たせそうか確認したい際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。